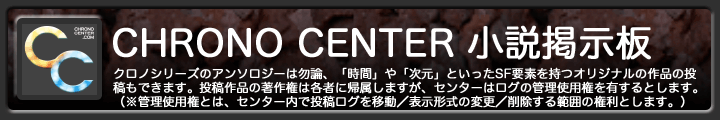| |
第128話「ほのかな歪み」
その後、クロノ達はギロチンが天井からぶら下がるコンベヤ床の部屋に来ていた。
そこでもルッコラはしばし観察すると、魔法陣を描いてサーバントを呼び出してしまった。
クロノ達はそこでもエイリアスを受け取ると、サーバントは消えて罠が無効化された。
その次の通路では、かつてはまるまじろが転がってきたものだが、ここも通路へ入ってすぐの所でルッコラがサーバントを呼び出して無効化するという流れを実行し、全く問題無く進むことが出来た。
次の部屋は落とし穴だらけの部屋であったはずだが、ここでもルッコラはサーバントを呼び出して無効化するとう一連の作業をして普通の床を歩く様に堂々と渡りきってしまった。その次も城の壁面にまるまじボンバーが転がってくるはずだが……以下略。
次の部屋も次の部屋も、かつては大勢のモンスターと遭遇したものだが、ルッコラはそれら全てが無かったかの様に、遺跡探検をするツアーガイドのごとく彼の考察が展開されながら進んで行った。そして、ビネガーがかつていた場所までたどり着いた。
「ふむ、この魔法陣を超えた場所が最後だと良いですねぇ。私もさすがに疲れました。さて、皆さん向かいますか」
エントランスホール同様に魔法陣から転移すると、そこは長く深く降りる階段があった。
ルッコラはこれまで同様に周囲を調べるとサーバントを呼び出すことに成功する。一通りの行動を終えると言った。
「これで私たちは合計で8体のエイリアスを受け取りました。ディアブロス、魔王のしもべ、まるまじボンバー、ソーサラー、ナイトゴースト、セーブポイント、ジャグラー、バンプット……これらのサーバントはそれほど強いものではありませんが、それぞれ特殊能力を持っています。それぞれのサーバントでこれらの能力を活用すると良いでしょう。本来であれば吸収してしまえるものですが、今回は歴史的な調査もありますのでご容赦ください。さて、行きますか」
……オウォーゥ。
「?」
何かの声がした気がした。
だが、クロノ以外は誰も気がついていないようだ。
気のせいか。
階段を下りて行く一行。
クロノはこの後の部屋が何の部屋かわかっていた。
それ故に気のせいといっても油断は禁物に感じた。
最後の段を降り、そこに開ける暗い闇への入り口をくぐり抜けた。
ゆっくりと部屋の中央へ進む。懐中電灯の光で辺りを照らすと、前方に何かが座っている様に見えた。
「誰だ。」
クロノの問いかけに、前方の何かがゆっくりと衣擦れの様な音を起こして振り向いた。
その顔はしわがれているが、間違いなく危険な人物であることを確認出来た。
「あたしのことよね?そうよね?……うふふふふふぅ、ようこそ、我が家へ。まさかこんなに早くにあたしのアジトがバレるなんて思っても見なかったわよねぇ。まったく、あたし達のやることなすこと全てに立ちはだかるのが………あなたの顔だったのよねぇ。ぐふふぅ、でも、飛んで火に入る夏の虫とは、あなたみたいのを言うのよねぇ」
しわがれた声で「彼女」は言った。
すると後方をずしんずしんと音を立てて何かが入ってくるのが聞こえる。
振り向くとそれはヘケランだった。しかも一体ではなく、複数体がどんどん入ってくる。
「あたしの可愛い坊や達、存分に遊んであげるのよねぇ。をーほっほほほほほほほほほほほ!!」
「!?」
ヘケラン達が襲いかかる。クロノが抜刀して切り掛かるがあまり効いていない。
フリッツが防御の為に魔力を集中すると、ダイヤプロテクトフィールドを発動させた。
「く、道を確保しなくては。私のフィールドもすぐに破られる。何か手は無いか!」
「……ここで行き止まりなんだ。ここは、元は魔王の部屋だったからな」
「なんと。……では袋小路」
「そういうことだ。……って、ん?……なんだアレ?」
クロノは中央に小さな空間の歪みみたいなのを見つけた。
これは魔法の力で空間に光が満たされなかったらわからないほどのものだったであろう。
「シズク!そこにある歪みを調べてみてくれ!」
「え、歪み?……あ、アレのこと?わかったわ!ちょっと待って」
シズクがシーケンサーをバックから取り出して辺りを計測する。
「……これは、ゲート」
「やっぱりか。よし、開けるか?」
「うん、やってみる。ポチョ!」
「ぽーっ!」
彼女の胸元からぽちょが飛び出した。……相変わらず何処で眠っているのだろうか。
ポチョは早速ゲートを開き始める。しかし、あまりにも小さすぎて簡単に開きそうにない。
「時間が掛かりそうだわ。とにかくこの場はポチョが開くまでみんなで持ちこたえましょう!」
「あ、あの、どういうことですか?」
「詳しくは後だ。今はとにかく生き残ることを考えろ!」
「わかりました。メキャベ君、やってやろうじゃないですか」
「はい。」
ダイヤフィールドが破壊された。
ヘケランの巨体による体当たりで耐えきれなくなったフィールドが、まるでガラスが砕け散る様に細かく破砕され飛び散った。そこを抜けてクロノが再び切り掛かる。魔力を込めた刀の力によってヘケランの肉体が刻まれる。今度は確実に両断され、その体はなんと光となって消滅してしまった。
その消え方を見てルッコラが言った。
「サーバント!?そうか、この数は全てヘケランのエイリアスです」
「ヘケランのエイリアス?」
「そうです。実体を出している存在を倒さない限り、永遠にエイリアスは出続けます」
「本体は……マヨネーか!」
クロノが方向を転換しマヨネーへと切り掛かる。しかし、マヨネーはその攻撃を寸での所でひょいと、いとも簡単に扇子で受け止めた。だが、明らかな違いが生じていた。その持つ手は先程までのしわがれたものではなく、妖艶な程に青白く透き通る様な美しい肌をしていた。
「……うふふ、そんなに求めてくれて嬉しいわ。女は求められて綺麗になるのよね。どんな男もあたしの美の前にはひれ伏すの。…さぁ、あなたもあたしの僕になるのよねぇ~~!!!」
若返ったマヨネーの瞳が赤く光った。
周囲からハート形の炎が形成され、クロノへ襲いかかる。
「ぐあぁああ!!!」
その炎をもろに食らってしまい、衝撃で強く地面へ叩き付けられる。
不思議にもその炎は熱くはなかったが、衝突した時の衝撃は常識を外れた重圧だった。
以前の「彼」も同じ炎を使っていたが、これはそれまでを遥かに超えている。
何が彼をそれほどまで強くしたのだろうか。
これはこの時点ではそんなことを思う暇等無かったが、間違いなく浮かび上がる疑問だ。
そこへ追い打ちをかける様に炎が襲いかかるが、フリッツが彼の前へ出て左手に出したダイヤのシールドで炎を防いだ。
彼も両の手でその衝撃に耐えたものの、その重圧でクロノ諸共後方へ押された程だった。
クロノがよろめきながらも立ち上がり構える。
「うふふ、良いでしょぉ?この炎。思わず痺れちゃう程だと思うわよね?そこのオジさんもじんじん感じちゃったんじゃないかしら。もっともっと、痺れさせてあげちゃうのよねぇ~♪」
後方ではシズクがサンダガでヘケランの室内への侵入を妨害している間に、ルッコラとメキャベが力を合わせて一体一体ヘケランを滅していた。
「ぽーーーー!!!!」
ポチョの声がする。
振り向くと緑色に輝くゲートが空間にぱっくりと口を開けた。
クロノは言った。
「みんな、先に入れ!」
その声を聞いてポチョとシズクが入った。ルッコラ博士とメキャベ氏がそれに続く。
クロノはフリッツを先に入らせると魔力を集中し始めた。
「な、なんなの!?」
マヨネーが突然の状況の変化に困惑していた。そして、クロノの攻撃に備えた。
クロノも構える。……だが、次の攻撃は無かった。
「……消えた」
クロノ達の姿は消え、そこは先程までの闇に沈む静寂へ戻っていた。
|
|
|