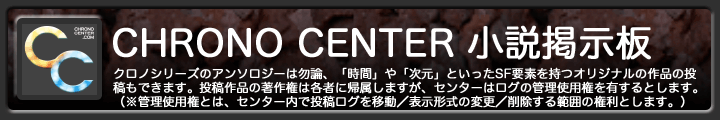| |
ガルディア城下町、トルース。かつては活気あふれたこの町も、パレポリ兵が闊歩するようになってからは通りに人影が絶え、人々はそれぞれの家の中でパレポリ兵の足音を聞くたびに首をすくめていた。
その北に位置するリーネ広場も例外ではなかった。遊び盛りの子供も、井戸端会議に興ずる婦人も、のんびり散歩を楽しむ老人も、今はいなくなってしまった。
広場の中央には、その音色を聞けば幸せになれると言われているマールディアの鐘がある。しかし、ガルディア王国が崩壊してからは、誰もその美しい音色を聞いた者はいない。夕暮れがせまり赤く染まり始めた鐘の下に、一人の少女が座り込んでいた。
夕焼け空よりも赤い服を着た少女は、束ねた金髪を風になびかせながら物思いにふけっていた。革の手袋をした手の中には一通の手紙がある。
ねえちゃん。あなたは今どこにいるんだ? オレは世界中あなたを探して旅を続けてきた。この間までいたエルニドでは、『運命』と、そして『時喰い』と戦って、倒して平和が訪れた。憎いあいつももういない。でも、オレはあなたを取り戻さない限り旅を止められない。
偶然知り合えたあなたの研究仲間から渡された、あなたからオレへの手紙。確かに受け取って読んだよ。かつて時を超える壮大な旅をした事、その旅によって得たものや失うかもしれないもの。そして、オレ自身の事……。あんまりいろいろ書いてあるんで、オレの頭ではまだよく理解できない所もある。でもオレに必要な事が書いてあるのだろうって事だけは判る。何しろ、頭脳明晰・才色兼備のねえちゃんからの手紙だからな。
「キッド!」
突然呼ばれて少女ははっと顔を上げた。知り合いの初老の婦人がこちらに歩いてくるところだった。
「ああ、やっぱりここにいたのね。さっき、あんたらしき人を見たってエレインが教えに来てくれたんだよ」
「だからって、わざわざ探しに来なくてもよかったのに。パレポリ兵に見つかったらいろいろヤバいんだろ、ジナばあちゃんは」
苦笑しながらキッドは立ち上がる。この老婦人、歳に似合わず時々こういう危ない事をやらかすのだ。しかもジナはなぜかほかのトルースの民よりも厳しく見張られているため、家から出る事はなおさら危険なのである。なぜなのかはジナに訊けば教えてくれるのだろうが、あえてキッドは訊いていない。
「パレポリなんて目じゃないさ、そんなにあたしを見張りたいならもっと巡回の間隔をせばめなきゃ駄目だね」
えへんと胸を張ってみせるジナにキッドは呆れた。と、ジナは腰にあてた両手を下ろし鐘を見上げてつぶやいた。
「でも、不思議だねえ。こうしてここに立っていると今にも鳴りだしそうなのに、うんともすんともいわないなんてさ」
「ジナばあちゃんはこの鐘の音を聞いた事があるのか?」
「もちろんさ。昔はよく鳴っていたんだよ、とても綺麗な音色でねえ。でもパレポリが来てからはまったく鳴らないんだよ」
どうしても噂に名高い音色を聞こうとしたパレポリ兵が揺すっても叩いても、小さな音さえたてなかったという逸話まであるくらいなのだ。
「それよりもキッド、今夜はうちにいらっしゃいな。みんなあんたに会いたがっているんだよ」
かつて一緒に育ったみんなは、数年前家が焼けてからはジナの家に住んでいる。キッドも、旅に出る前はそこに住んでいたのだ。
「ありがたいけど、オレを泊めたりしてパレポリに見つかったら、もっとジナばあちゃんがヤバくなるんじゃないの?」
「見つからなきゃいいんでしょう。それに、もし見つかったとしても、うちにいる間は指一本たりとも手出しさせないから安心しなさい」
任せなさいと言わんばかりに胸をたたき、軽くウインクする。そんなジナを見て思わず笑みがこぼれた。
「判った。後でそっちに行くよ」
「もう日が暮れるし、早くいらっしゃいよ」
そう言ってジナはもと来た道を戻っていった。
キッドはまた一人になる。
もう一度手の中の手紙を見ると、ある文に目がとまった。
その一文だけは、キッド以外の人物に呼び掛けている。
ジャキ。
懐かしい、その名前。遥か遠い記憶がよみがえる。
ジャキ。
オレを……いや、もう一人のオレを探しているというその人物。ねえちゃん、教えてくれよ。あいつは今、どんな思いでオレを探しているのだろう?
その時、かすかだが奇妙な音を聞き取ってキッドは不審げに辺りを見回した。幼い頃によく聞いた、機械の動作音によく似ている。どうやら音源は広場の出口とは反対側の、この鐘よりも奥のようだ。つまりは自分の背後からなのだが、振り返ってみてもそれらしいものは見当たらない。
草むらの中だろうかと端まで歩み寄り、草をかき分けて驚いた。丈の高い草の間から、上へ向かう階段が現れたのだ。人が寄り付かなくなったため手入れもされず、伸び放題の雑草が覆い隠してしまったらしい。
呼び寄せられるように、草をかき分けながら上っていく。一歩ごとに、あの音が強くなっていく。けれども上っているうちに、動作音だけでなく、人の声が聞こえるようになった。そんなところに一体誰がいるというのだろう。
上り終わった所には変わった装置が左右に一つずつ置いてあった。それは幼い日、ねえちゃんの部屋で見た設計図と同じものだった。名前は確か、テレポッド。
その二つの装置の間に、黒いゆがみが出現していた。そして周りには、遠い昔に出逢った人達が集まっていた。いや、よく見るとただの立体映像である事に気が付く。隅の方にこれもねえちゃんの部屋で見覚えのある装置が据え付けられていた。この装置が目の前の映像を映しているらしい。
彼らは、何か感慨深げに話しあっている。やがて、金色の巻き毛を揺らして、快活な女性が黒いゆがみへと進んでいった。ふっとその姿がかき消える。続いてカエルの姿をした剣士が。それを見て、彼らの別れの場面なのだと判った。
そして今、夕闇色のマントを着た人物が、黒いゆがみへと歩き出す。
『サラを探すの……?』
オレンジ色の髪を一つに束ねた少女が、彼に問いかける。振り向いた彼は、答える代わりに口元に小さく笑みを浮かべた。それは、懐かしい彼の、今まで見た事のない表情。
彼が黒いゆがみの中へ姿を消した所で、映像は終わっていた。
ふと思いついて、まだ握りしめたままの手紙を改める。封筒の内側に、何か小さなチップのようなものが張り付けてあった。どうやらこれがあの装置を動かす鍵になっていたらしい。ねえちゃんらしい、用意周到なサプライズだった。
笑おうと思ったのに、頬を涙が伝っていった。それをぬぐいもせず、キッドは黄昏色の空を見上げる。紅い夕陽が涙に潤む目にまぶしくて、それでも目をそらす事なく、いつかまた出逢う、どこかにいる彼に遠く呼び掛けていた。
私は、ここにいるよ。
Fin
|
|
|