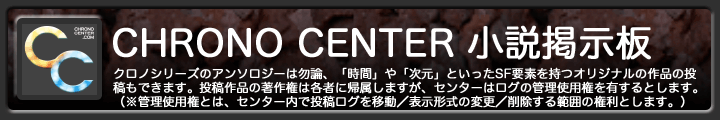| |
人が動く気配を感じ、ガルディア国王は手元の書物から顔を上げた。こちらをうかがいながら玉座の前を通り過ぎようとしていた娘が、ぎくりとして立ち止まる。音を立てないよう細心の注意を払った忍び足も、かつて多くの激しい戦いを経験した王には通じない。
「どこへ行くのだ?」
簡潔な質問には深い意味はなく、単に娘の所在を明らかにしておきたかっただけの事である。問われた方は王に向き直り後ろ手に扉を開けながら、少し早口で返した。
「ちょっと、食堂に……」
「また料理長に菓子を作ってもらうのか」
「うん、まあそんなとこ」
えへへ、と照れ笑いをしながら言う娘に、あきれたような視線を向ける。甘いもの好きは母譲りだ。
「じゃ、行ってきます!」
扉を開くと同時に身をひるがえし、娘はまるでばね仕掛けのおもちゃのようにすっ飛んでいった。やれやれとため息をつき、書物を閉じながら一人つぶやく。
「いったい誰に似たのやら……」
「もちろん、私たちでしょう」
くすくす笑う声と共に、王妃がもう一つの玉座の後ろから現れた。ドレスのすそを軽く引きずりつつ王のそばへ歩み寄ってくる。
「子供の頃の私は本当におてんばだったけれど、あの子には負けるわね。きっと私だけじゃなくてあなたにも似たからよ」
「元気なのはいいがちょっと度が過ぎるのではないか。 どこぞの誰かに弟子入りしたいとも言っていたから、そのうちそっちにも似てきそうだしな……」
ひじ掛けに頬杖をついた王は、「どこぞの誰か」と言うところで書物の表紙をもう一方の手で軽く二、三度叩いた。書物に目を落とした王妃が、題名を見て軽く目を瞠る。
「『ガルディア史録』……。またそれを読んでいたのね。どこか気になる事でも?」
「いや、どこにもない。完璧すぎるほどまともな歴史書に仕上がってるよ。……編さんした張本人が実際に見てきた事まで盛り込まれているなんて、微塵も判らない。将来あいつ、物書きになっても食っていけるぜ」
王族らしからぬぞんざいな言葉で、この場にいない編さん者の腕を控えめに評する。皮肉にも聞こえるそれが褒め言葉である事を、王妃以外の誰が判っただろう。
ガルディア史録は、建国千年を記念して編さんされたものである。「ガルディア」と冠されてはいるが、はるか古の原始時代やかつて栄えた魔法王朝など、ガルディア王国が建国されるよりも昔の出来事まで事細かに記述されている。
たった二人の編さん者が、膨大な文献を三年という短い歳月で完成させたこの書物は、ガルディアだけでなくパレポリの公共施設にも配布され、多くの人々に読まれる事となった。それ以降、編さん者たちは「ガルディアの二大賢者」と呼ばれている。二人とも王と王妃の共通の知人で、「命の賢者」と呼ばれているのは世界最高の腕を持つ老刀鍛冶、「智の賢者」と呼ばれているのは若い天才科学者の女性だった。王が「あいつ」と呼んだのは後者である。
「これを読むと、昔の事を思い出して、懐かしくてな。アルバムを見るつもりでつい手に取りたくなるんだ」
穏やかな微笑みを浮かべて、表紙をなでる。そんな王を見て、王妃もまた微笑んだ。
城内にある食堂は地下に造られているが、内装や照明のためにむしろ明るく清潔感のある空間となっている。その雰囲気の良さから、食事時以外でもちょっとした交流の場として利用されている。
「お待たせ!」
言葉と共に会場からひょっこりと顔を出すと、とたんに叱声が飛んできた。
「遅い、ラト!」
一番入口に近いテーブルに座っていた赤い服の少女が、こちらを振り向き怖い顔でにらんでいる。一つにまとめてお下げにした金髪の揺れ具合が、振り向く勢いの良さを物語っていた。
「ごめん、キッド。ここにたどり着くまでに、いろんなところで捕まっちゃってさ。とくにパパの前を通る時は冷や汗ものだったよ」
「あんまり遅いから、料理長が出した果物の盛り合わせ、二人で全部食っちまうところだったぜ」
照れ笑いをしながら歩み寄ってくるラトを呆れ顔で見るキッドの前には、一口大に切り分けられた数種類の果物が乗った皿が置いてある。そして真向いには、白いマントの人物が慎ましく座っていた。目深にかぶったフードの奥に見える口元に微笑みを浮かべている。
「大変でしたね、ラトディア様」
「だめだめ、姫もサマもなしって言ったでしょ? ラトって呼んでよ、ミラ」
両手を腰に当ててラトはぷうっとふくれてみせた。ミラと呼ばれた白マントの人物がくすりと笑う。
「判りました、ミラ」
ミラは、数日前にラトとキッドがガルディアの森で野生モンスターに苦戦していたところを助けてくれた。フードとマントのために容姿はよく判らないが、声から判断するとラト達と同年代の少女のようだ。生き別れの両親を探して放浪中だという事以外はあまり自分の事を話したがらず、名前も持っていないと言うのでラトが仮にミラと名付けた。
初めて会った時から、ラトは妙にこの少女の事が気に入り、あまり乗り気でないミラを熱心に城に招いた。初め、騎士達には不審がられていたが、気づいた時にはいつの間にか打ち解けていた。王や王妃も、この謎に包まれた少女の事をすぐに信頼するようになった。その事をキッドが不思議がっていたが、彼女自身ミラを悪党だとは思えなかったのですぐに気にならなくなった。キッドの育て親に言わせれば、ミラのように自然と周囲に信頼される人は結構多いのだそうだ。
ラト達が町に出るためにガルディアの森を通る時、護衛をするのがミラの役割となっていた。本来、姫であるラトが町に出るのはあまり好ましくない事であるはずだが、王も王妃もこの事に関してはなぜか厳しく言う事はなかった。だからラトも行きたい時に自由に町へ行く事が出来た。
「よっしゃ、見つからないうちにさっさと行こうぜ」
残りの果物を手分けして食べ終えると、キッドが立ち上がりながら楽しそうに言う。
「ミラは、森を抜けたらまた城に戻ってね。みんながわたしの事探し始めたらどうにかして時間稼ぎをして」
「判りました」
微苦笑を浮かべてミラが答える。三人の少女はまるでイタズラを始めるかのようにこっそりと行動を開始した。
「あの、陛下……。ラトディア様をご存じありませんか?」
困惑した声をかけてきたのは、ラトに礼儀作法を教えている侍女だった。
「さっき見かけた時は、食堂に行くと言っていたが……」
嫌な予感を覚えながら答えると、侍女は謝礼の言葉を残して食堂へ向かった。王妃が心配しながらもどこか楽しげに言う。
「また逃げているのね、ラトは」
「困ったものだな。誰かさんと同じだ」
ため息をつき、軽く首を振りながら隣の玉座を見やると、案の定王妃は楽しげに笑っていた。
「本当に。似なくても良いところばかり似ているようね」
「しかし、なぜこうも礼儀作法の時間だけ抜け出すんだ? そんなに嫌う理由は何なのだろうな」
「堅苦しいのが苦手なのかもしれないわ。私もそうだったから」
もう一度ため息をついた時、さっきの侍女が慌て顔で戻ってきた。
「食堂にもいらっしゃいませんでした。料理長の話では、少し前にどこかへ行かれたとか……」
「やはりか……。こんな事なら、さっき引き留めておけば良かったな。行き先に心当たりはないか?」
侍女が首を横に振ったのと、入口から現れた別の人物が声を放ったのはほぼ同時だった。
「ラト姫なら、今頃キッドと一緒にリーネ広場でしょうね」
どことなく面白そうにこちらを見ているのは、先ほど話題になっていた智の賢者だった。彼女の言葉に、さすがの王妃も呆れてしまう。
「リーネ広場って……また町に行ったのね、あの子は。でもどうして判ったの?」
「そりゃ、森の入口でミラとばったり会ったからね。ラト姫には何とかごまかすように言われていたみたいだけど、あれじゃ丸わかりだもの」
苦笑しながら室内に入ってくると、いたずらっぽい視線を王に向けた。
「それで、どうする? 今なら遠くに行ってないだろうし、連れ戻すのは簡単よ」
「え?」
独り物思いにふけっていた王は、自分に視線が集まっている事に気がついて我に返り、ラトの脱走の件に頭を切り替えた。
「いや、今日のところはラトの自由にしてやろう。……手間を取らせて悪かったな」
王から直接ねぎらいの言葉をかけられた侍女は恐縮しながら下がっていった。その背中を見送りながら、王妃が小首をかしげて問う。
「どうしたの?」
「ああ。前から思っていたんだが、ミラは一体何者だろうな」
王は正面にたたずんでいる智の賢者の顔を見た。彼女も真剣な面持ちでうなずいている。
「私もずっと考えていたわ。知っている気がするのだけど、後もう少しというところで思い出せないの」
二人の顔を見比べ、王妃もあごに手を添えて考えてみる。
「もしかして私達、どこかでミラに会った事がある……?」
「それをこれから確かめに行こうと思うのだ。いつもはラトがそばにいて訊くに訊けなかったから、良い機会だと思ってな」
王は玉座から立ち上がった。
「ミラは今、どこにいる?」
|
|
|