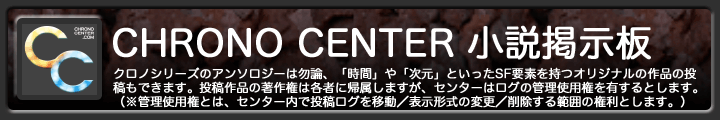| |
見上げると、そこには空があった。
厚い雲のあいだから時折覗く、灰色の小さな破片めいたものではあったが、確かにそれは空だった。
かつて、彼が「未来」において見た果てしない青空とは比べるのも憐れな、狭い、くすんだ空ではあるが、それでもこの時代に生きる者たちにとって、それは未来に住まう者たちにとっての青空に優るであろうこと、想像に難くない。
彼は、視線を地上に戻した。
一面の銀世界。
おそらくは、世界を覆うこの色彩が彼の命があるうちに変わることはない。それでも、すべてを拒み続けてきた雪原はいつしか人を受け入れ、「村」と呼ばれるようになり、そして今、そこは「街」として機能し始めるに至った。
銀世界に、鮮やかな緋色。
世界が空を得てからも、ごく稀にしか見ることのできない落日で染め上げたかのような、深い紅のマント。この街ではすっかり馴染みとなった、彼を彼と知る、何よりの目印だ。
雪を踏みしめて、彼は丈高い身体と小さな荷物を街の中心へと運んでいるところだった。すれ違う人々が、彼の姿を認めるつど目を瞠ったり、弾かれたように慌てて会釈をしたりする。
彼は敬われ、畏れられ、……そして、恐れられていた。何しろ彼は、今となっては世界で唯一の、魔力を持つ人間であったから。彼の、明らかに人のものとは異なる容姿を不審なものと見る者が少なくないことも、また事実。
街の者たちの態度を、彼は意に介さない。少なくとも、表面上は。畏怖されることにも、異端視されることにも、彼は慣れていた。
目的地の程近くに、開けた一画がある。「公園」というには粗末なものだが、子供たちがはしゃぎまわるのには充分な、ちょっとした広場だ。
横切ろうとして、彼はそこで足を止めた。
子供たちの一群れが、何やら騒いでいる。めずらしくもない光景だが、それを見咎めて、彼はなぜか顔を顰めた。無言で、子供たちの群れる場へと近づく。
彼に気づいた子供たちが、互いを突っつき合って慌てて逃げ散っていく。いじめっ子たちに囲まれてうずくまっていた男の子が、顔を上げて彼を見上げた。
「……おじちゃん」
「また、お前か」
「おじちゃん」と呼ばれたことを気にくわないと思ったからなのかどうか、彼の声は不機嫌そのものだ。たいていの者は彼のもの言いと表情に尻込みするものだが、この子にはそれがなかった。泥に汚れた顔を、男の子は笑ませた。
「えへ、ありがと。おじちゃん!」
「礼を言うよりも、自分で何とかしろ。……以前にも言ったはずだ」
その言葉通り、これまでも何度か似たような場面に出くわして、結果として彼はこの子を助けたことがあった。
不愉快だ。と、彼は思う。
一つには、この子をいじめていた子供たち。
かつて「光の民」と呼ばれた、天に浮く大陸から来た者たちであることを、彼は知っている。未だ残る差別意識。光と地、それぞれを分かつ定義など、とうに消え失せたというのに。
二つには、目の前の子。
不当に虐げられながら、なぜ黙ってそれに耐えるのか。その行為は、自分自身だけでなく仲間たちに対する侮蔑をも認めることだということに、気がつかぬほどには幼いわけではあるまいに。
そして三つには、自分自身。
別に正義を気取るつもりなどない。それに寄りかかるつもりも。そんな資格は、自分にはないのだと知っているから。
弱いものは強いものに取り込まれ、滅するが世の摂理。それでも、数を恃んでそれを己の強さと取り違える者たちに対する不快感は抑えようがない。たとえそれが、子供の喧嘩にすぎないのだとしても。小さな芽も、やがては巨木となり、多くの者たちの頭上に影を落すことになるのではないか。と、そう考えてしまう。知るはずのない未来を知る者の、それは杞憂であるのかもしれないのだが。
「ごめんね。でもね……」
彼が気を悪くしたことを察したらしく、男の子の声は小さくなる。
「でも、何だ?」
無愛想に、それでも話を聞くつもりはあるらしく、彼は広場の隅に置かれたベンチを示した。翻る紅のマントの後をついて歩きながら、男の子は濁した言葉を続ける。
「うん、でもね、ボクとあいつらがケンカしちゃ、やっぱりダメなんだよ」
「…………?」
ベンチに腰かけて足をぶらぶらさせる男の子に、彼は訝る顔を向けた。
「えっとね、つまり……、あいつらは『光の民のほうがえらいんだぞ』って言うけど、もしボクが『地の民はそんなこと認めない』って言ったら……、ええと」
「再び袂を分かち、争うことにさえなるかもしれない、と?」
幼いゆえの語彙の少なさに、男の子はもどかしそうに首を振ったりしたが、聞く者は言わんとすることを正しく理解した。うなずいてから、男の子は不安そうに彼を見上げた。
「……おかしいかな?」
「……いや、おかしくない」
不安と、そして安堵が、同時に彼の胸に湧いた。滅びた国と共に過去の領域へ消えたはずの選民意識が、未だ幼い世代にさえ根づいていることへの不安と、それを危惧する、やはり幼い者が存在することへの安堵。
……託す価値はあるかもしれぬ。
内心にうなずいて、彼は傍らの荷に手を置いた。
黎明(後)へ続く
|
|
|