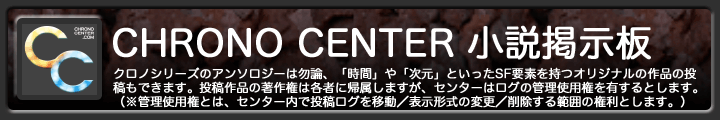| |
第110話「暗闇の理由…中編」
「ハイド、お前は隠れてなさい。何が有っても、出てはならぬぞ。」
「父上、僕も戦います。」
「だめよ、ハイド。あなたが居なくなっては、誰に私達の思いは伝わるの。あなたは生きるのよ。」
「母上…」
母上は僕にそう言うと眠りの魔法を掛けて僕が眠りについた後、二人は僕に完全結界を張って地下室の闇に隠した。
父上と母上は、封主(ほうしゅ)といい、特に母上は代々伝わる太古の結界を守る家系だった。
封主の仕事は結界の張られた遺跡を清らかに保ち、その安定を来るべき主が現れるまで維持する事に有った。
実際、その結界は簡単な力では解く事は出来ない特殊な魔力で作られていて、現代のどんな魔法をもってしても解呪は不可能と言われていた。だが、解呪は不可能でも結界自体が危険な代物で、これを悪用しようと思えば相当な力になるものと思われていた。
故に、危険であっても遺跡を狙う者は何時の時代も絶えない。
封主はそんな盗賊から遺跡を守る役目もになっていた。
僕らの一族は数千年の昔からこの場所を守り続けてきたことで、他の魔族には無い特別な力を授かってもいた。
それは、完全な防御。
僕らの一族は遺跡を悪者から保護する為に、究極の防御フィールドである「パーテクト」を生み出した。
パーテクトは完全な防御結界であり、どんな攻撃でも無効化する究極の防御魔法。
プロテクトとリフレクは本来別の魔法であり、しかも魔法攻撃効果を相殺するには同じ属性のフィールド、または倍の出力の反属性フィールドが必要になる。さらに物理防御フィールドであるプロテクトを、完全プロテクト化するには莫大な魔力出力が必要となる。
勿論、このパーテクトはこの条件を満たしても簡単に誰もが使える魔法じゃない。
まず、1人で使う事は不可能で、魔法を形成するには水属性と天属性の使用者を必要とする。そして、水属性の詠唱者は封主の血を受け継いでいる必要が有る。封主は結界から出て来る魔力を長い年月浴びて得られる、特別な斥力フィールドの形成能力の素質を持ち、魔法の発動に欠かせない。誰もが魔力を浴びたからと使えるものじゃない理由はそこにある。
一度形成されたフィールドは能力者以外は解除できず、長時間高い防御性能を誇る。故に、その力を欲する者もまた絶えない。僕らは決められた婚姻関係を結び、その力を外に広めずに大切に守り続ける必要があった。
僕の父はティエンレン一族の中でも珍しい、天の魔力を受け継ぐ一族「イジューイン」の長の次子。イジューイン一族は門外不出の究極の天の魔法を使えることで、古代の魔王もその力に手を焼いたと言う。故に、イジューインは魔王の命令を聞きはしなかったティエンレン一族の一つだ。
僕らの一族の婚姻の条件は、体制に組み込まれない確実な力と極めて純度の高い天属性の能力者だったから、イジューインと母の一族であるスイソ族はとても仲が良かった。当然の如く交流も有り、決められた婚姻とは言っても、知らない仲ではなかった。実際、両親はとても仲が良かった。
だけど、あの日、全ては崩れ去った。
「どうしても、抵抗するんだね。究極の絶対防御とやらを、見せてもらおうじゃないか。」
長い髪をさらさらと揺らす長身の黒装束の男は、赤く禍々しい輝きを放つ宝石をはめたステッキを持ち、構えた。
「誰にもこの先へは進ませない。」
「行くわよ、あなた!」
「おう!」
二人は構え集中した。
すると、彼らの周りを分厚く透き通る氷の結界が張られた。その広さは背後の彼らの村をもすっぽりと包み込むほどだった。しかし、黒装束の男は余裕の表情で言い放った。
「児戯だね。これなら、君らの忌み嫌う彼らよりずっと劣ってるよ。こんなもの、僕自らが手を下す必要は無いね。」
「何だと!!」
夫が反発する。その瞬間、フィールドが揺らいだ。無理もない、彼ら夫妻自身、これほどのフィールドを形成するのは生まれて初めてのことなのだ。
妻は挑発に乗らずじっとこらえて集中し、フィールドを安定させた。
黒装束の男はそんな彼らの焦りを見透かすように微笑むと、宙を見上げた。すると、彼の視線の先から彼同様の黒装束を纏った1人の少女が現れた。
「私の仕事ですか。」
「そうだ。君の仕事だ。」
「分かりました。早速遂行致します。」
少女はそう言うと、静かにふわりと降り立ち、夫妻の結界に向けて手をかざした。
「…効果属性、天。制御属性、水。フィールドプロテクト解析。ESバランス解析。属性効果に特殊修正確認。フィールドプロテクトに時空反応を確認。ES確認、ティエンレンF、水。ティエンレンM、天。目標を消去します…」
その後、夫妻の結界は少女の力によって崩壊した。
彼らは圧倒的な力で彼らの村を焼き、それに関わる全てを攻撃した。
…僕は幸い見つからずに難を逃れ、気がついた時には先生の家のベッドで眠っていた。
彼女の話では急襲された後、たまたま通りかかって僕を見つけたらしい。
完全な防御結界に包まれた僕は、完全に崩壊していた地下室の土砂と岩の下敷きになっていても、無傷で眠っていたらしい。二人の結界は完璧に機能していたんだ…。
僕の力はどんなに頑張っても完璧にはならない。それは、僕がどんなに頑張っても半分だからだ。
もう1人の力…天の使い手がいなければ、僕は完璧にはなれない。
先生は僕に彼女が知り得る全ての知恵を授けてくれた。
彼女には恩義が有る前に、母親の様な掛け替えのない人だと思う。だから、彼女の悲しむ姿は見たくない。…でも、この戦いは、引くわけには行かない。
僕には分かる。
この女の中に流れる熱い魔力の底流に、深く暗い闇の様な負の魔力が流れているのを。
彼女はあの時村を襲った彼らの仲間に違いない。
彼女を締め上げれば、彼らの情報を得る事が出来るまたと無いチャンスだ。
確かに僕は不完全だ。
でも、…今は1人じゃない。
「ティタ、君の力を僕に貸して欲しい!」
「うん、任せて!」
「ランタ、君を頼りにしてるよ。」
「…貸しはメディーナ駅前のヘケラン丼だ。」
「へへ。」
少年が杖を横一文字に構える。
彼に続く様に少女が魔力を集中する。
「(…パーテクト。)」
少年を中心に円を描くように魔法陣が形成される。
少女が魔力を地面へ向けて注ぎ込むと、青白く輝く紋様が浮かび上がり、一気に氷のドームが形成された。魔法陣の輝きが周囲をうっすら青く照らし、空間に居る者たちを浮かび上がらせた。
女が一瞬眉を動かした。
少年はそれを見てニヤリと微笑した。
|
|
|