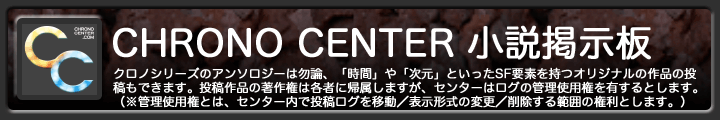| |
薄暗い通路を進みながら、プロメテスは連綿と語る。それは彼が「生まれる前から」探し続けてきた、死に瀕した星に蒔くための「種」にまつわる話だった。
「マザーが……イエ、まだ情報センターと呼ばれる施設のホストコンピュータだった『彼女』が保有していた古い情報から、ワタシはある興味深い人物のデータを見ツケマシタ」
L.アシュティア。AD1000ごろのガルディアという王国にいたとされる工学博士。彼女が長からざる生涯のあいだに遺した「時空と並行世界に関する研究」のファイルが、情報センターの膨大な電子資料のなかには眠っていた。
「断片的で、しかも研究そのものが彼女の死によって中断されてしまったようで、実証されるには至っていないのですが、コレが打開策にはならないだろうかと、ワタシは考エテイマス」
「具体的にはどうするんだ?」
注意深く周囲を見回しながら、リュートはプロメテスに問うた。
プロメテドーム。マザーとリンクするコンピュータの制御するドームだが、すでにRシリーズによるダミー回路への待避が完了しているため、ガードロボの攻撃を受けることはない。だが、この時代に生きる者の習性として、気を抜くことができないのである。時代がかった愛用のサーベルは、抜き放たれて利き手に納まっている。
「時を、越えることはできないデショウカ?」
ヒトのように表情を変えることのないロボットであるが、プロメテスの表情はこのとき昂揚する気持ちに輝いたようにも見える。
「時を、越える?」
「……どういうこと?」
ヴァンとティアも、相次いで訪ねた。
「ドリームプロジェクトからのメッセージにもある『ラヴォス』という怪物を、監視しているひとがいるノデス。実際にお会いしたことはないノデスガ、どうもこの世界の機械文明とは違った科学に精通した方らしく、あるいは……」
「……やり直す、というのか?ラヴォスとやらが現れる前の時代から?」
鉄兜のような頭部を、プロメテスは器用にうなずかせた。リュートが、金色の大きな目を瞬かせて嘆息した。
「途方も無い話だな」
言いながら、彼は仲間が一人歩みを止めたことに気づいて振り返った。
「……?どうした、ティア」
「うん。……うん!やろうよ、それ!」
「え?」
「歴史を、変えちゃおう!」
「ほ…本気か?ティア」
「本気だよ。生き物の世界を取り戻すためには、何でもするって決めたよね?だったら、やろうよ。ね?ヴァン!リュート!」
頭の高さのずいぶん違う二人は斜めに視線を交し合ったが、やがてどちらからとなく苦笑した。
「そうだね、他に目ぼしいネタがあるわけでもない」
「ああ、何てこった。人間てヤツぁ追い詰められるととんでもないことを考えてくれる」
弱肉強食の世界を、決して「強」ではない立場で生き抜いてきた者たちである。無鉄砲なばかりではないはずだ。彼らは、この突拍子もない作戦に確かに光明を見た。それは、本当に暗い闇のなかだからこそ判別できたような、小さな小さな光明だったのかもしれないが。
「では、これを預けておきマショウ」
プロメテスが、ティアに何やら小さなものを差し出した。
「これは……、種?」
「新型の情報媒体デス。このなかに、アシュティア博士の『時を越えるマシンに関する研究資料』のデータをダウンロードしておきマシタ」
「えっと、じゃあ……」
不意にドーム内に警報が鳴り響き、ティアの質問は遮られた。警報に続いてそこここの扉が開閉する音が重なり、ドーム内の静穏は一瞬にして破られた。
『侵入者アリ!侵入者アリ!B-1.B-2ぶろっくノがーでぃあんハ、タダチニさーちと迎撃を開始セヨ!』
「何だとっ!?マザーとのリンクは切ってあるんじゃなかったのかっ!?」
リュートは反射的にプロメテスに疑惑の目を向けたが、当のプロメテスも狼狽している様子だ。
「まさか!そんなハズは!?」
困惑するプロメテスのサーチシステムが、このドームには異質な反応を捕らえた。彼が向いた方向に、ヴァンが素早く目を向ける。何度となくロボットたちと闘った経験のある彼女も見たことのないモデルの、小さな虫のようなロボットが単眼をちかちかと光らせていた。
「新型の斥候ロボットか!」
素早く照準を合わせ、ヴァンは装備していた愛用のオートライフルのトリガーを引いた。すばらしい精度でロボットの単眼を破壊する。だがすでに、自分たちを取り巻く状況はこれ以上無いほどに悪化してしまっている。
「伏せて下サイ!」
プロメテスが叫ぶ。だが間に合わない。
「うわあっ!」
「きゃあっ!」
ガードロボが横様に放ったレーザービームが、四人の肌と装甲を灼いた。
「ぐっ、くそうっ!」
後ろの二人を庇う形で広範囲に負傷を追ってしまったリュートが、呻き声を上げる。
「リュート!」
「リュートサン!」
駆け寄る仲間たちを振り解くように、リュートは立ち上がった。そして叫ぶ。
「ティア!行け!」
「……え?」
「逃げろ!」
「な…何言ってるの!?そんな、わたしだけ」
「種を!」
「あっ!」
ティアだけでなく、ヴァンもプロメテスも、顔を上げる。周囲を警戒しながら、プロメテスも言う。
「行って下サイ。ティアサン。南の大陸の、『死の山』の麓へ。そこにいる監視者に、その種を渡して下サイ。お願イシマス」
言い終わると同時に、プロメテスは三人を抱えるようにして後方に押しやった。それとほぼ同時だった。
「プロメテスッ!!」
複数のレーザービームが、プロメテスの背に横殴りの驟雨となって命中した。ドーム内が一瞬、漂白されたかのような白い閃光に満たされる。
「プロメテスーッ!」
自らも重ねて傷を負いながら、二人の人間と一人の亜人は、血の通わぬ仲間の名を叫んだ。ティアの手のなかで小さな種が、こんなときだというのに奇妙に温かい感触を彼女に伝えていた。
|
|
|