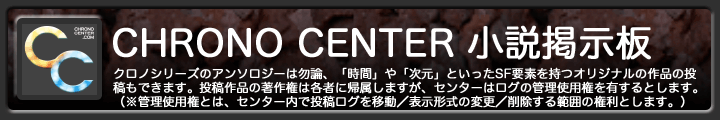| |
AD1000 ―花を咲かせる者たち―
すっかり見慣れた星空だ。短くない眠りの間に星座の位置が変わったことなど、小さなことだ。自分が生まれたとき、空に星が存在することは知っていたが、それを見ることが可能であることを知ったのはずいぶんと後になってからだった。
ふと、ロボはそんなことを思った。
森は暗い。焚き火はまだ燃えていたが、弱々しい炎は周囲を照らす力をすでに失っていた。それでもロボには火を囲んで眠る仲間たちの姿が見える。
“暗い世界で生きていかなくちゃならないから”
彼を生み出した者のひとりが、そう言ってアイセンサーの集光装置のプログラムを入念に調整している姿を、今でも思い出すことができる。
「思い出す」……?
いや、それは正しくない表現なのではないか?なぜならその時、自分は未だ「生まれてはいなかった」のだから。
それでもロボは知っている。会ったこともない、「生みの親たち」の想いを。
微かな葉鳴りを、ロボの集音装置は拾った。火を挟んだ向かいで、「彼女」の面影を強く宿す少女が寝返りを打ったようだ。悪い夢でも見ているのか、時折煩わしげに首を動かす仕草が気にかかる。
彼女の左隣で突然、くしゃみが上がった。周囲で眠る者たちの幾人かが、眠りながらもびくりと身をすくませるほど盛大なそれを放ったのは、硬質の赤毛を好き勝手に跳ねさせた少年だった。
“こいつに全てを背負わせて……、もしかすると、おれたちはとんでもない酷いことをしてるのかもしれない”
まだ生まれてさえいない、「生物」ですらない自分に、記憶のなかの「彼」は痛いほどの想いを込めて言ったのだ。
“ごめんな。いっしょに闘えなくて……、ごめんな”
何やらむにゃむにゃ言いながら手足を縮めて眠る少年に、ロボは「彼」の姿を重ねる。
風が強くなってきたようだ。木々が茂らせた葉をざわめかせ、消えかかっていた焚き火は空気を孕んで再び赤々と燃え上がる。しかしそこで燃え止しを使い果たしたのか、風が再び落ち着きを取り戻したとき、それはひと筋の煙を残して今度こそ消えた。辺りを完全な闇が覆う。
月のない夜だ。人の目はもはや役目を為さないはずだ。だが、ロボは確かに自分に向けられている視線に気づいた。星空の微かな光を集めて、獣のそれのように闇のなかで光る双眸がその主だった。
「……余計なことを考えているようだな」
双眸の持ち主が、闇の先から面白くもなさそうに声をかけてきた。彼の声もまた、ロボの最も古い記憶を揺さぶってくる。
“心を与える……だと?つまらん。それこそ要らぬ苦痛を強いるだけだ”
絶望の世界に生きることを生まれる前に定められた自分の行く末を、最も危惧した者。突き放すかのような声音の裏に、ひとの目の届きづらい心の奥に、自分自身で持て余すかのように不器用な優しさを抱いていた「彼」が、かつて自分に贈った言葉。
「今は休め。せめて、赦されるあいだくらいは安らうことだ」
ロボの返事を待たずに再び眠りに落ちた彼を、そして先の二人の少年と少女、さらに金の髪を束ねた高貴な面差しの少女、豪気ながら彼女と共通するけはいを持つ佳人、異形の剣士……、決戦を前にわずかな休息を取る戦士たちを順繰りに見回して、ロボは胸中に呟いた。
ああ、自分は今再び、共に戦う仲間を得た。
もう一度見上げる空は、相変わらずの星の海。この輝く夜空がいつの日か止まぬ砂嵐に閉ざされるとは、知っていても到底信じられぬ。
いや、もう二度と、「この星を死なすこと」は赦されない。「土を耕した者たち」と、「種を蒔いた者たち」のためにも。
今度は、自分たちがこの星に「花を咲かせる」番だ。
「彼ら」との思い出は、遥か未来に築かれたものだ。まだ生まれてさえいない者たちとの思い出を抱くのは、おかしなことかもしれない。だが、
「見てくれてイマスヨネ?ドン……、レイ……、アルノ……、リュート……、ヴァン……、そして、ティア……。アナタたちの育てた種は、もうすぐ花開キマス!」
了
|
|
|