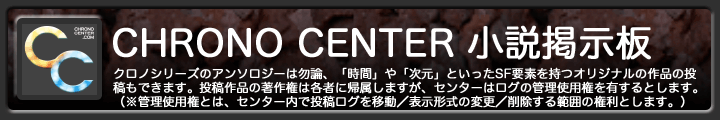| |
第85話「湿った闇の中で」
「う、うぅぅ……」
ひんやりとした感触が頬に伝わる。
ざーざーと流れたり、滴る水の音が聴こえる。
全身に悪寒が走りとても寒い。
開いた視界に入ってきたのは暗闇だった。
深い闇にほんのりと輝く光苔の緑の光が若干の明かりとなって、辺りの景色がどのような物かを伝えてくれる。
周囲の壁は一面石で出来ており、氷柱のようなものも見える。どうやら洞窟の中らしい。
「(…俺は…)」
最後に残っていた記憶は、船長に促され救命ポッドに駆け込んだ事だった。その後激しい揺れが襲い、意識を失ったのだろう。
一体ここは何処だろうか。そして、あの後どうやって自分はここに行き着いたのだろう。体を起こして周囲を見回した。だが、まだ目が慣れておらずよくわからない。ただハッキリ分かる事は、仄かな緑の光と体の感覚だった。
「痛っ…」
あまり信心深い方ではないが、ここは正直に神に感謝すべきだろうか。
奇跡的に体は若干の痛みはあるものの異常はなかった。だが、全身ずぶ濡れで非常に寒い。洞窟の温度も低く、寒さが堪える。
目が慣れてきてから周りを眺めると、洞窟のおぼろげな姿と共に何人かの人が倒れているのが確認できた。そのうちの1人に仲間の姿があった。彼は彼女のもとに近寄り、口元に耳を近付ける。
彼女は呼吸をしており、どうやら無事で眠っているだけのようだ。体の方も出血は見られず、無事にみえた。
安堵した彼は、彼女の名前を呼びかけた。
「シズク、シズク。」
「うぅん、なーに?………え?ここは?」
「洞窟の中らしい。俺にもよくわからない。」
シズクが起き上がる。
寝ぼけてハッキリとしている様ではなかったが、どうやら彼女も異常は無いらしい。
「あ、クロノ、……私達、船が渦に巻き込まれたのよ…ね…?」
「あぁ。」
「でも、ここは………?」
「俺もさっき目覚めたばかりだ。わからない。だが、奇跡的に助かったことは確からしい。」
「そうね。…!、他にも助かった人がいるのかしら。」
彼女はすっくと起きて立ち上がる。だが、立ち上がった瞬間、全身ずぶ濡れのため、洞窟の冷気も相まって悪寒が体中に走る。しかし、今はそんなことに気圧されているわけにはいかない。震えを押さえて急いで他の人を調べた。
二人の他には四人の乗り組み員が倒れていた。いずれも彼らが同乗したポッドにいた人達で、その中には船長も含まれていた。
シズクが辺りをよく見ると、壊れたポッドの破片らしきものが周囲に幾つも散らばっていることが確認できた。どうやらポッドはここまでバラバラになりつつも全員を運んだのだろう。
「船長さん、大丈夫ですか?」
シズクが船長の頬に手を置き呼び掛ける。
「……。」
「…そんな。」
シズクは脈を計るために首の頸動脈を探ったが、既に脈は無く体も冷たかった。
「他の人は!?」
急いで他の者の安否を調べたが、彼女の期待とは裏腹に既に亡くなっていた。しかし、それを素直には受け入れられない彼女は、エレメント「ケア」を発動したが、既に体は受け付けなかった。
「…私達だけなのね。」
「…あぁ。」
二人は黙祷し、4人の冥福を祈った。
シズクは近くに散乱していた流木をかき集めて魔法で火をつけた。
ボッという音と共にパチパチと燃え上がり、辺りを仄かなオレンジの光が包む。
「…まずは冷えきった体を温めましょう。幸いここは密閉されていない。さっきから向こうから風の音が聴こえるもの。」
クロノは彼女の意外な程の冷静な状況判断に驚いた。確かに通気が無い場所に風の音など聞こえるはずはない。ならばこの風は確かに地上との接続を伝えるシグナルといえた。時々彼女の冷静さには驚かされる。
「ここはどこか見当がつくか?」
「…わからないわ。海底深くの鍾乳洞の様にも見えるわね。もしそうなら、死が若干伸びたに過ぎないわね。シーケンサーで調べられたらなんとかわかるかもしれないけど、シーケンサーも渦潮の衝撃で壊れてるみたい。」
彼女はそういってゲートシーケンサーを見せた。確かに動かず何も表示されない。
「直せないのか?」
「そうしたいのはやまやまだけど、荷物も飲み込まれて消えてしまったから、精度の良い工具が無ければ、これの修理はここではとても無理だわ。」
「そうか。」
二人は暖をとって体が十分に乾いた頃を見計らって動き出すことにした。
洞窟はシズクの言った通り、奥から風が入ってきていた。風の来る方向へ進むと、細いながらも人が通れる道があった。そこを通り抜けると大きな空洞に通じ、何やら向こうの方で音が聴こえる。その音は何かを削る重機の音の様だ。
「この空洞には道が無いみたいだけど、何かの作業音がするわね。」
「しかし、出るにはどっかに穴を開ける必要があるな。」
クロノが構えようとすると、シズクがそれを制止した。
「待って、こっちに向かって掘ってるわ。それも近い!」
シズクはそう言うと壁から離れて待機する。
クロノもそれに倣って後方に退いた。
すると壁からの音が大きくなり、遂に目前の壁が大きく煙りを上げて突き破られた。
現れたのは、人が1人乗れる大きさのドリルのついた重機だった。
二人は開通に両手を上げて喜んだ。
「に、人間!?………あ、あんた方どっから来たべ!?」
作業員の魔族の男性が驚いて二人に問う。
無理もない。本来なら人なんて居るはずも無い場所から現れたのだから。
「わからない、だが、有難う!これで出られる。出口はどっちへ向かえば良い?」
歓喜し訪ねるクロノに、半ば流される様に答える魔族の男性。…彼自身、あまりに飲み込めない事態に、流される様に答える他に何も浮かばなかった。
「んぁ?お、おぉ。出口はこの坑道を真直ぐ行って、突き当りを左に曲がればあとは看板出てるべ。」
「そうか!サンキュー!よし、行こうぜシズク!」
「はいな!」
二人は足早にその場を去って行った。
作業員は呆然として口を開けて座席に座りながら、そのまま後ろ姿を見送っていた。
作業員の言に従い道を進むと、上り勾配の道に自然になっていた。
二人は作業員の言葉の正しさを実感して、無事に脱出できることを喜びつつ夢中でただひたすら歩き続けた。そして前方に真っ白に輝く光で満たされた出口が見えた。
出口を出ると、そこには大きな機関車のプラットホームらしきものが展開されていた。線路が何本も敷かれてあり、周囲には牽引車の無い貨物車に多くの石が積まれて置かれていた。積まれている石はトルースで見た石にも似ているが、色が少し違うようだ。どうやらここは鉱山だったのだろうか。
二人はホームに上がった。そこに一台の機関車が前方からゆっくり入ってくるところだった。大きな駆動音と線路を擦る車輪の金属音が耳障りに聞こえる。
目前の機関車は完全にプラットホームに停止した。すると、後方から何やら音がする。その音はレールを駆動する音、後方から登場したのは石を満杯にした沢山の貨物車だった。最後尾の機関車が牽引している。
貨物車はゆっくりとホームに入り、既に止まっている機関車の連結部と連結した。それが終わると、最後尾の機関車が連結を外し、再び鉱山へ向かってゆっくりと出発する。
「この列車に乗って行こう。」
突然クロノが言った。
彼女は彼の提案に同意したいところだが、自分達は切符も無い。しかも客車でも無い貨物車に乗るのは不安があった。
「大丈夫かしら?」
「別に構わないじゃないか。乗れれば街に入れるんだろ?だったら使わない手はない。」
「まぁ…そうね。」
彼女は苦笑しつつも同意した。確かに一番手っ取り早い。
クロノはそう決めると、足早に先頭に止まっている機関車の運転席の方へ駆け寄った。そして、中にいる魔族の男性に声をかける。
「すまない!一つ頼みたいことがあるんだ!」
クロノの呼び掛けに、魔族の男性は面倒そうにゆっくりと振り向く、男は呼び掛けた相手を見て驚愕の表情を見せた。
「え、ぇえ!?!お、おい…、あんた…昔タンスから出たことあるか?」
「タンス???……え?もしかして、君はあの時の!?!」
驚いた事に、彼は昔ゲートで出た先に住む住人だった。まさかこんな形で会えるとも思わず、お互いがお互いの存在に驚くと同時に、懐かしさが込み上げた。
「本当に覚えが有るのか!?!マジかよ!?うぉお!久々だなぁ!懐かしい!どうしてまたこんな所に?」
「う、うーん、説明が難しいんだが…ははは。」
クロノは今まで起こったことを順を追って簡単に説明した。その時にシズクを紹介した。運転士の名はカルロと言い、今もメディーナに住んでいるらしい。
「…ははは、あんたはいつも変わったことになってんな。ま、安心しな!このMBー1は長距離を走るマシンだからな、交代用の仮眠室が後部にある。あんたらはそこに乗ると良いぜ。ここで会ったのも何かの縁だ。楽しく行こうぜ!」
カルロはそう言うと二人を機関車に乗るよう促した。どうやら出発時刻らしい。
彼は二人が乗り込んだのを確認すると最後に乗り、施錠確認を行うと運転席についた。
「後方よーし!左右よーし!前方よーし!…出発進行!」
出発の起動音が鳴り響く。
システムがオンラインになりエンジンが駆動を始めると、車内にその駆動音が伝わり少々煩く感じた。
機関車がゆっくりと動き始める。
線路の継ぎ目を踏むガタンゴトンという音が徐々に早くなる。
空いた窓から風がそよぎ、運転席から見える視界は次々に通り過ぎて行く。鉱山が遠くに見える頃には安定した駆動音に変わっていて、随分と煩く無くなっていた。
いや、慣れただけかもしれないし、風の音で紛れたのかもしれない。だが、心地よい眠気を誘う揺れが、特にそう感じさせたのかもしれない。
二人は疲れていた。
沢山眠っていたかもしれないというのに、体と言うものはまったく不思議なものだ。
様々なことがあり、ようやく安全が確保されたことに安堵したこともあるのだろう。二人は暫く深く眠りについた。
列車は草原の中を駆け抜けた。
|
|
|