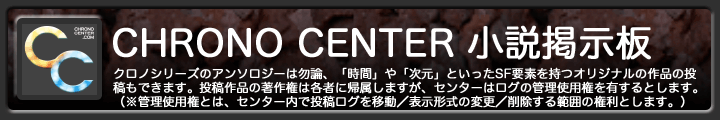| |
AD2288 ―種を蒔く者たち―
部屋は暗い。広くもない空間を照らすのは、機械油に浸された「紙縒り」に火を灯しただけの粗末な光源だった。くすんだ色の壁にゆらゆらと影を躍らせながら、これまた粗末なデスクに臥して眠っているマール・ティア・ルディオを、哨戒から戻ったエイラ・ヴァン・スペーディアは見つけた。ヴァンが手にしていた物をデスクに置くと、ティアはぼんやりと目を開き、数秒の後、弾かれたように上体を起こした。
「お疲れだね、ティア。でも、こんなところで寝ちゃあ風邪ひくよ」
「……ん、大丈夫。ごめんね、ヴァンには大変なことしてもらってたのに、わたしばっか……」
しおらしげなことを言いながらも思わずあくびが漏れてしまい赤面する妹分の頭を軽く撫でて、ヴァンは持ち帰った荷を解いた。銃器や固形燃料、保存の利く食料などに混じって、新旧の情報保存媒体がデスクの上に広げられる。
「リュートはまだ帰ってきてないのかい?」
ティアとともにデスクの上の物を仕分けしながら、ヴァンは訊ねた。こくりとティアがうなずく。
「うん、まだ時間がかかると思う。情報センター跡、遠いよね」
「だね。でも、今までにない大きな希望だよ。これに辿り着けたのもティアのおかげだ」
荒廃したこの世界では貴重とも思える華やかな美貌をほころばせるヴァンに、ティアも微笑み返した。
「うん、これからだね。がんばらなきゃ!」
********************
この時代の人類は、統合された「歴史観」を持たない。AD1999の大災害に続く「大反乱」と呼ばれる事件以来、人類社会は細かに分断され、互いに情報や物資そして人材や技術の類をやり取りする術を失っていた。情報センターをはじめとするコンピュータ群に蓄積されてきた膨大な量の「情報」は、もはや人類が所有するところではなくなっているのだ。
「大反乱」。AD2032、この時代唯一大災害以前から稼動していた情報センターのホストコンピュータ「マザー」が、突如内部と外部とを問わずアクセスを遮断したことに端を発する「機械群の人類に対する叛乱」を指す。
AD1999、「ラヴォス」と呼ばれる謎の存在が引き起こした大災害により、人類はその数を激減させていた。「決起」以前にマザーが密かにアクセスしていた世界各地のコンピュータの官制下に置かれていた情報、流通、軍事に至るすべての設備、機能が「人類を抹消する」ことを目的として稼動したとき、それに抗するだけの力を人類は持たなかった。
「実に65000000年に及び『万物の霊長』として君臨してきた人類の、憐れなる末路である」と記すのは、マザーと直結する「ライブラリ」と呼ばれるコンピュータだ。
********************
「はっ!血も通わねえような連中に、人類の歴史がどーのとか言ってほしくないもんだぜ!」
「……はあ、すみまセン」
「あ、いや、なにもお前さんに言ってるわけじゃ」
「……はあ、すみまセン」
止むことのない砂嵐のなかを、奇妙な二人組が歩いている。
口数の多いほうは極端に背が低い。子供とも見紛う小柄な体格だが口調や所作から察するに、どうやら立派な大人の男のようである。ただし人間ではないようだ。砂が目や口などに入り込むのを防ぐため、顔の下半分を何重にも布で覆い、目深にフードを被っているため判然としないが、その風貌は両生類のそれを想わせる。この時代、人類以上に見かけることの少なくなった「亜人」であるらしい。
もう一人は、いや、「一体は」と言うべきかもしれない。大柄なほうは二足歩行型ロボットだった。砂嵐に溶け込む鈍い黄土色に塗装されたボディには、刻印されたばかりのシリアルナンバー「R-66Y」の文字。
真新しい引っかき傷のようなその文字を見ながら、小柄なほうが訊ねた。
「お前さん一体だけしか連れ出せなかったのは正直痛いが、残りの連中はどう動く手はずになってるんだ?その点も『彼ら』は考えていたんだろ?」
「少しずつ……、マザーの官制をかわしながらになるので、本当に少しずつになりマスガ、地方のコンピュータにリンクしているラインをダミーにすり替えていく作業を行いマス。デスガ、『彼ら』には細かなプログラムを施すだけの時間が与エラレマセンデシタ。ワタシたちに与えられた命令は、実におおまかなものでしかアリマセン」
「ははあ、まあしょうがないか。なにしろ300年近くも前に慌てて打った布石だもんな。ちょっとくらい大雑把だからって文句言っちゃ、バチが当たるってもんだ。……そら、見えてきた。俺たちのお屋敷さ」
小柄なほうは親指を立てて、そこに在ると知らされていなければ見過ごしてしまうであろう岩くれのような影を指した。この粗末な建物が、人類に残された、おそらく最後で最強の砦だった。
********************
マール・ティア・ルディオが「それ」を発見したのはいつごろだったか。マザーの侵入をロックできるコンピュータを確保するのが困難な状況で、しばらくのあいだそれは保管されるだけで、開封されることがなかった。埃まみれで一部熱で変形している耐衝撃素材ケース。そのなかから現れた、古い情報保存媒体。煤けたラベルには、丁寧な文字運びでこう書かれていた。
「種を蒔く者たちへ」
多忙で命がけの日々のなか、それでもティアがそのディスクの存在を忘れたことはなかった。なぜと訊かれても、ティア自身それを説明することはできないだろう。だが一見浮世離れした、文学的とも取れる短いタイトルのなかに、切実なほどに現実を見据える者の息吹を、彼女は確かに感じたのだった。
自分の直感は正しかったとティアは確信している。まだ結論は出ていないが、それでも希望に繋がる細い糸口を確かにつかんだのだ、と。
扉を叩く音が、ティアの思考を浮き上がらせた。傍らでヴァンが旧式のオートライフルを構えながら誰何する。馴染んだ声が帰還を告げるのを聴いて、彼女は銃を下ろし、扉を開いた。
「お疲れ、リュート。野晒しガエルにならなくて何よりだったね」
「哨戒ロボットに回収されて焼ガエルになるくらいだったら、お前に食われたほうがまだ『まし』ってもんだ」
グレン・リュート・ナノは砂の積もったフード付マントを脱ぐと、「ケロロ」と咽喉を鳴らして笑った。
「……いたの?『メッセージ』の通りに」
扉の向こうを気にしながらティアがリュートに問う。紹介が済むまで待つようリュートに言われている「彼」が、そこにはいる。ティアもヴァンも承知はしていることだが、それでもこの時代に生きる者に「彼」の姿は抵抗があるだろうから。
「おう、いたいた。連れてこられたのはヤツだけだったけどな。よう、入ってくれ」
リュートの最後の一言は扉の向こうに向けられた。「お邪魔致シマス」と、丁寧な挨拶とともに現れたロボットを見出して、ヴァンの持つオートライフルの銃口がわずかに持ち上がったが、すぐに下がる。
「はじめマシテ、プロメテスと申シマス」
プロメテスの挨拶に人間たちはしばらく応えなかったが、やがてティアがひそめられた声で応じた。
「えっと、はじめまして、わたしはマール・ティア・ルディオ。彼女は……」
「エイラ・ヴァン・スペーディアだ」
緊張を解かぬまま、ヴァンも名乗る。その後再び重い沈黙が落ちたが、ティアが一枚のハードディスクを見せながらプロメテスに質問した。
「教えて、プロメテス。『彼ら』……あなたを生み出したひとたちのこと。彼らは、わたしたちに何をさせたかったの?」
二人の人間と一人の亜人は、またも重い沈黙を以ってロボットに対した。先人が遺した記録と自分たちの置かれた状況の矛盾を埋める鍵を、彼が握っているはずだった。それを、何としても手に入れなければならない。プロメテスはくるくると首を回して何やら考える素振りを見せた。時折「ぴぽぽ」と鳴る電子音が、どうしても人間たちの負の感覚を刺激してしまうが、これはどうしようもない。やがてプロメテスは言葉を選ぶように語りだした。
「……ワタシたち『Rシリーズ』のプログラマーたちが想定した『敵』は、マザーではアリマセン。自己のリプログラミングとアップグレードを繰り返し、かつて人間によって施されたプログラムを廃除してきたマザーから、ワタシたちが当初の予定通り生産されたのは、単に初期のセーフティープログラムが格段に優秀だったという理由に他ナリマセン。『彼ら』は当時、マザーこそ人類を守護する存在となると考エテイタノデス」
|
|
|