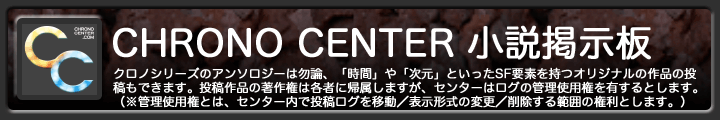| |
AD1999 ―土を耕す者たち―
……トルース地方で検知された「熱源」を巡る、ゼナンとチョラスの紛争。さらにガルディア王国において一時期研究が進められていたとされる、「時を超えるマシン」の存在の是非を巡って行われた研究者たちの査問。それに次ぐ粛清。パレポリの暗躍。第二次人魔対戦。それに起因する亜人の大量虐殺。
「……現代ってつくづく平和だわ」
持っていた資料を、すでにデスクに山積みになっている資料の上に投げ出してルッカ・レイ・ブリーズトは嘆息した。
若い。独立したラボを与えられるほどの年齢に達しているようには到底見えないが、しかし彼女はすでに「博士」の称号つきで呼ばれる身分だった。肩口で切り揃えられたくせのない褐色の髪は、水の流れを想わせる。そこから覗く横顔は、文句なしの美貌。
「そんな話をするために、わざわざ呼びつけたのか?」
不機嫌そうな声が背後からかけられたが、彼女は動じる色もない。
「そうよ、感謝なさいアルノ。あんたってほっといたら引きこもってばっかでカビが生えそうなんだもの。たまには外の空気も吸ったほうがいいわ」
レイの碧空を想わせる蒼い瞳が、縁なしの眼鏡ごしに皮肉気に……というよりはいたずらっぽく輝く。
ジャキ・アルノ・シュヴァルツェンの、レイのそれと対を成すような紅い瞳が険を増した。尖った耳殻を持つ耳も、神経質そうにぴくりと動く。
こちらも若い。レイよりはやや年かさだろうが、それでも世間からは「ヒヨッ子」呼ばわりされる年齢には違いない。そして彼も、レイ同様他者から呼ばれるときは、名前の後に「博士」だの「先生」だのといった称号やら敬称やらが付くのがお決まりだった。ただしレイの見るところ、アルノ自身はそれを相当に疎ましく思っていることは間違いない。「人」とは違う者たちのなかで育った彼は、人から与えられる「称号」というものをすでに好まないのかもしれない。
「よっ、揃ってるな、お二人さん」
アルノがレイに向かって何か言い返そうとしたとき、タイミングよくドアが開いて三人目の人物を招き入れた。
「遅いわ、ドン。遅刻魔!」
「呼び出しておいて待たせるとはいい身分だな、所長というのは」
幼馴染たちの手酷い挨拶に、クロノ・ドン・シューマはがっくりと肩を落とした。好き勝手に跳ねさせている硬質の赤毛も、心なしかうな垂れたように見える。
「そう言うなよ。これでもけっこう忙しいんだぜ」
言いながら、若き所長さんは持っていたトレイから湯気の立つコーヒーカップを三つ、ブリーズト女史のデスク……正確にはデスクに積み重なった資料の上に置いた。
「……何か、解ったのか?」
置かれたコーヒーカップが一つ、また一つと持ち上げられるつど顕になる資料に目を落として、ドンは訊ねた。「ラヴォス」というワードプロセッサの文字がやたらと目につく。
「『これ』が元凶よ」
すべてのカップが卓上から退いたところで、レイは資料の一束をつかみ上げた。彼女が差し出すそれを、ドンはコーヒーを啜りつつ受け取る。紙の束は、ずしりと重い。片手で器用にそれをめくって、ドンは斜めに目を通していった。
「よくまとめたな、これだけのものを、……あれだけの時間で」
「まあ、『基』は出来上がっていたしね。って言うかね、『基』にちゃんとまとまりがあったらわたしが徹夜することもなかったのよ。ねえ、アルノ?」
「基」を提供した者は「じろり」と彼女を睨んだが、それ以上は言及しなかった。代わりにアルノは、もうひとりの幼馴染に面白くもなさそうに訊ねる。
「どうするつもりだ?おそらくは、もう間に合わない」
「どうするも何も、闘うしかないさ。勝たなくても、負けないための手は打つつもりだ」
この場に、彼ら以外に事情を知る者がいたとしたら、ドンの言葉を悲壮と取ったかもしれない。だが実際に彼の言葉を聞いた二人の幼馴染たちは、むしろ呆れたように、あるいは共感したように、小さく笑ってうなずいた。
「あんたって案外心配性だったのね、アルノ。わたしたちの仕事は土を耕すこと。種を蒔いて芽吹かせるのは、次の世代の仕事よ」
分かっている、と、やはり面白くもなさそうにアルノは答え、窓の外に目をやった。雲一つない青い空が、どこまでも広がってこの星を包んでいるのが見えた。
「平和……か」
コーヒーの芳香とともに、アルノの口から呟きが漏れた。感情の読みづらい声音だ。このせいで彼はしばしば誤解を受けてきた。だが、この場にいる者たちには、彼の想いは正しく伝わった。それで充分だった。
後に「ラヴォスの日」と呼ばれる未曾有の大災害を数日後に控え、世界の片隅で交された、それは歴史に残されることの無いやり取りだった。
********************
「それ」が地上に姿を現してから三日目。例えばこの星の外からやって来たものが現在のあり様を見たとしたら、わずか三日前までのこの星の姿を想像することなどできなかったに違いない。
空は赤い。地上も赤い。そしておそらく、地中深くも煮えたぎる赤であろう。絶え間なく大地が……いや、星全体が鳴動する。炎の塊が天から降り注ぎ、死に瀕した星の肌を幾度となく灼いた。なぜこの星がこのような災害に見舞われたのかを知る者は少なく、災いをもたらしたものの正体を知る者はさらに少なかった。
それを知る者の数少ない生き残りである二人が、闇のなかで言葉を交わしていた。
「……ドンは結局残ったのか?情報センターに」
「ええ……、『プロジェクト』のデータを少しでも完全な状態で遺せるようにしたいって」
「ふん……、ばかめ。……だが、あいつらしい」
「ばかはわたしたちも一緒よ」
「……そうだな」
囁くかのような声音が、彼らにもう話す力が残されていないことを物語っていた。瓦礫の底のわずかな空間に折り重なるように横たわる二人は、互いの命が傍に在ることを確かめるように、残された力と時間を、互いの声を拾うことに傾けていた。
「……もっと、……もっと、わたしたちにできることって、無かったのかな」
「一握りの生き物がわずかな時間で星の運命を定めようなど、傲慢なことだ。……お前は、できる限りのことを成した。誇っていい」
傷ついた己の身体の上で、やはり傷ついた身体を、彼女が微かに震わせるのを彼は感じた。
「……うん、……ありがとう、アルノ」
「らしくないな。……いよいよ、焼きが回ったか?」
全身の力を使って、アルノは笑った。彼が嘲ると、決まって彼女は腹を立てて何か言い返してくる。これまで、ただの一度も例外はなかった。だが、
「……レイ?」
反応がないことを不審に思い、アルノは彼女の名を呼んだ。何が起こったのか、分かってはいた。それでも、彼はレイが何か言い返してくるのを期待したのだ。しばらく待って、彼は再び嘲笑した。自分自身を嗤ったのだ。
「……焼きが回ったのは、俺のほうだな」
それが、ジャキ・アルノ・シュヴァルツェンの、最期の言葉だった。
血に汚れた耐衝撃素材ケースが一つ、力を失った彼の掌から零れ落ちた。
ひときわ激しく大地が振動し、ほどなくして炎の雹が二人の亡骸を抱く建物の残骸にも降り注いだ。
|
|
|