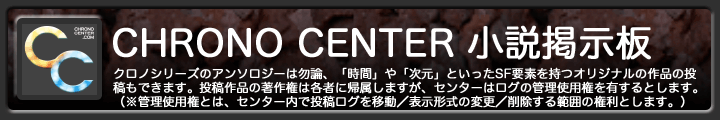| |
クロノプロジェクトシーズン2をご覧の皆様、いつも有り難うございます。
今年もあと僅かですが、お風邪など引かれていませんでしょうか?
今回は年末年始をゆっくりとお楽しみ頂けるよう、ちょっとばかり増量してお送りしております。
この制作も来年で8年目ですが、シーズン2に入ってクロノプロジェクトオリジナルの世界観が色々と出て来る様になりました。拙い文では有りますが、これからも頑張って書いて行くので、今後ともお楽しみ下さいましたら幸いですし、この世界を気に入って下さったら有り難いなと思います。
第111話「暗闇の理由…後編」
「…まさか、エインシェントの使い手がまだ生き残っていたとは。」
女は呟くように言うと、慌てるでも無く攻撃態勢を解いた。そして、前に立つ二人の屈強な男達に後方へ下がるよう命じる。
男達は彼女の命令に従うと、静かに後方へ退いた。
「…その魔法は厄介だけど、私達の力が効かない事と同様に、あなた達の力も使えない。…だけどその完全防御にも唯一問題がある。その魔法、何分もつのかしら?」
女の指摘は的を得ていた。
確かにパーテクトはその完全さ故に内側からも攻撃が不可能である。これは絶対防御を成立させる上で間違いなくぶち当たる壁であり避けられない。しかし、この防御にもほころびが有る。彼女が言う通り、維持する事がとても難しい魔法でもあるのだ。
この魔法は魔力供給自体は一度の発動で済むが、それを維持・コントロールするには例え魔族と言えども誰もが出来ることではない。しかも、それは「継承する血統内」ですら確実ではなく、故に婚姻関係を結ぶ相手との関係が考慮されもした。
だが、ハイドは彼女の指摘にも怯む事は無かった。
「ランタ、頼むぜ!」
「おう。」
ランタはハイドの頼みに待ってましたとばかりに集中していた魔力を前方へ向けて構えた。
「(ダークボム)」
ランタはなんとパーテクトフィールド内部で魔法を発動させた。しかも、なんと魔法効果は女達を中心に外で起こり、冥の魔力が女達を直撃する。
しかし、彼女は瞬時に冥のフィールドを張り巡らすと、直撃の効果を低減させた。そして、間髪入れずに右手から火の玉を、左手から氷の刃を出して攻撃する。だが、パーテクトのバリアフィールドは完全にその攻撃をはじき飛ばしてしまった。
ランタがそこに第二撃のダークボムを放つ。
今度は完全に彼女の目前で弾けた。彼女にはフィールドを張る暇もなかったはずだった。だが、彼女はその力をまるで受けなかったかのように平然とした顔で立っていた。
「…私に直撃を与えられたことはお褒めしましょう。でも、これであなた方の力量は把握しました。パーテクトとダークボムのコラボレーションは素晴らしい。でも、この攻撃にも限界がある。」
そう言うと彼女は静かに少年たちの方へ歩み寄る。
その右手からは水の魔力が、左手からは天の魔力が集中するのが感じられる。
「させるか!」
ランタが叫ぶ。
第3撃を用意していたランタが、前方からゆっくり近づく彼女に向けてロックオンする。しかし、そこに屈強な男二人が素早く彼女の前に盾となった。
「ツー!」
「カー!」
ダークボムが発動する。
漆黒の負のエネルギーが生けるものから急速に生気を吸い膨張する。その力は空間全体から奪い取るような引力となり、二人の男達に襲いかかる。
そして、ついに臨海に達した。
ドドォォォォォォォォォォォン!!!
それまでの二撃を大きく上回る威力が、周囲に巨大な爆発音と衝撃の振動を伝える。それはクロノ達にも伝わる。
「くっ、すげーな。やったか…?」
思わず呟くクロノだったが、彼は煙が消えて現れたものを見て驚いた。
いや、これは放った当人も驚愕を隠せなかった。
「マジか!?」
そこに現れたのは無傷で堂々と並び立つ男達と、その背後で笑みを浮かべる女性の姿だった。彼女が男の肩に手を触れると、男達は静かに彼女の側面へと並び立ち、道を開けた。彼女はそれが当然という表情でまっすぐ前方の少年達を見据えて、ゆっくりと歩き始めた。
彼女のヒールの靴音がコツコツとゆっくり近づく。
ハイドは自信たっぷりに近づく彼女に内心恐怖を感じ始めていた。いや、もう既に彼の背後にいる二人の仲間達の方は、完全に彼女に圧せられていた。しかし、パーテクトが有る限り、彼女は自分に触れる事は叶わない。いくら近づいても彼女が触れることは起こりえないはずなのだ。だが、彼女はそんなことは全く問題無いと言わんばかりに、さも余裕だという表情で自信たっぷりにゆっくり近づいてくる。
「…なかなか楽しかったわ。でも…」
彼女が遂にパーテクトのバリアフィールドに右手で触れる。すると、彼女の水の魔力が徐々にフィールドの水の魔力に反応して同化を始めた。
「!?」
同化を始めた魔力が、今度は徐々に彼女の方へ制御が移り始めた。そして、彼女の左手がフィールドに触れた。
その途端…
パキィィィィィィィィーーーーーン!!!
…フィールドは粉々になり、キラキラと輝く塵となって舞い散る。
「そ、…んな、どお…し、て……?」
ハイドには一瞬何が起こったのか分からなかった。
それと同時に言いようの無い恐怖が、足先から駆け登ってくるのを感じた。
砕け散ったフィールドの欠片が、仄かな青い光となって辺りを照らしている。
前方の彼女は、微笑みながら腰を下ろし、その両手を彼の肩に伸ばす。
「…え?」
彼女は、少年を優しくそっと抱きしめた。
「…良く頑張ったわ。良い子ね。でも、私には残念ながら効かないの。気を落とさないでね。」
彼女はそう耳元で囁くと、彼のポケットから静かにプレートをとり出した。そして、微笑んでゆっくりと立ち上がると、プレートを自身の持つプレートを出して近づけた。
すると、なんと少年たちのプレートから全ての呪印球が飛び出して浮かび、眩い輝きを端って融合した。4つの呪印球は、1つの黒い冥の呪印に変化したのだ。
呪印球はそのまま彼女のプレートに吸い寄せられるように近づくと、プレートが反応して新たな呪印を収納するくぼみが真ん中に出来上がった。呪印はその新たなスペースへ静かに収まった。
「では、これは返すわね。」
彼女が少年たちのプレートを持ち主に手渡した。
手渡された本人は、もはや完全に戦意を失い、その成り行きに任せるかのごとく受け取るしか出来ていなかった。
「さようなら。」
彼女はそう告げると、ゆっくりと靴音をコツコツ響き渡らせて闇の中へ消えた。
少年はその場に崩れた。
クロノ達はそれを見て急いで駆け寄った。
「おい、大丈夫か!」
クロノの問い掛けに少年は我に返るように振り向くと、ゆっくり立ち上がった。
「…恥ずかしい所を見せてしまった様だね。…確か、チームポチョさん達だね。まぁ、見ての通り、傷は無い。大丈夫だ。」
少年は静かにそう言うと、手に持ったプレートに目を落とした。
「…無様だよね。でも、正直、完敗だった。あの途方もない魔力…まるで底が見えなかった。あの一瞬は…僕らには真似の出来ない次元かもしれない。」
彼は冷静に分析していた。
そんな彼の冷静さに、クロノは正直に驚いていた。
「あのさ…」
クロノが言いかけた時、少年の方が思い出したかのように言った。
「あ、そうだ。あなた方、見たところ強いですよね?」
「へ?」
「たぶん、僕ら以外で上位に残るとしたら、あなた方を入れると、他はメーガスかしまし娘。かファイアブラストでしょう。さっきの奴らはグリフィスだと思うけど、たぶん、彼らに勝てる術者って話になると、あなた方くらいだと思う。他の人達はきっと冥の呪印の間を探し廻るに違い有りませんし。」
「え、あ、はぁ。」
「僕はあなた方に託したい。」
「え?」
「その、感じるんです。あなたの中から僕らの一族が守ってきた力を。あなた方ならグリフィスに勝てる。そう思うんです。だから、この杖を持って行って欲しい。」
少年はそう言うとクロノに杖を差し出した。
クロノは少年の行動に困惑した。
「そんなことされても困るぜ。それに、俺は杖なんて使えないし。」
「良いんです。ここで逃してしまうぐらいなら、いっそあなた方に倒して欲しいんだ。」
「どういうことだ?グリフィスは何かあるのか?」
クロノの問い掛けに、少年は真剣な表情になった。
「…彼らは、たぶん僕の推測が正しければ黒薔薇だ。」
「なんだと!?」
「奴らは僕の村を焼き払ったんだ。それだけじゃない。奴らはエインシェントの使い手の根絶を狙っていた。」
「エインシェント?」
クロノは彼の言葉に全く理解できていなかったが、黒薔薇という存在には注目せざるを得なかった。そこにミネルバが口を開いた。
「失われた限られた種族間でしか継承されていない魔法の事です。先ほどの魔法…あなたはスイソ族の生存者ということですね。」
彼女の問い掛けに、彼はこくりと頷き言った。
「…ここへの潜入がどんな目的かはわからないけど、この試験が魔法を使う者を対象にしている以上、奴らのターゲットとなる対象は多いはずです。きっと、ただでは済まない。奴らに対抗するには生半可な力では無理です。だから、僕はあなた方に力を託す。必ず第三試験へ進んで欲しい。杖はそのための保険だと思って下さい。」
「保険?」
「そうです。保険です。」
クロノは彼の真剣な眼差しを見るまでも無く、黒薔薇という単語が出た時点で答えは決まっていた。
「君の願いは俺も答える用意がある。だけど、その杖は要らない。それは君の物だ。」
「しかし、この杖があれば…」
そこに少年の言葉を遮るように、ミネルバが言った。
「あなたの思いは分かりましたわ。でも、クロノさんの仰る通り、私もその杖はあなたが持つべきだと思います。その杖はあなたの一族が命がけで大事にした宝のはずです。それに、私達には私達の戦い方が有ります。人生は長いのですから、あなた自身が再挑戦することをお考えになって。」
彼女はそう言うとにっこり微笑み、彼らにケアルを唱えて傷を癒した。
少年は彼女の言葉に頷き、杖を仕舞った。
そこに、その成り行きを静かに見守っていたシズクが、少年に問いかけた。
「ねぇ、これからどうするの?例えば〜、私達に挑戦して奪い返すって手もあるわけよね?」
彼女の質問は確かに当然思い当たる話だった。
だが、少年は彼女に笑顔で言った。
「はは、託した以上、そんなことはしませんよ。でも、まだ試験を諦めてはいないですよ。まだまだ方法はある。では、また。」
そう言うと、彼らは闇の中へ消えた。
すると、舞い散っていた青い光も彼らが去るのを追うように消え去り、再び空間は闇に閉ざされた。
|
|
|