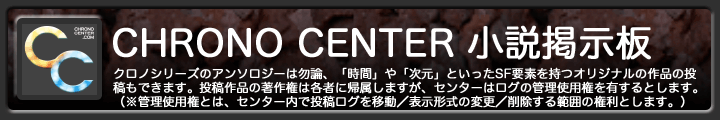| |
瞳の美しさを宝石に喩えた詩(うた)は、いったい何千篇あるだろうか。
この眸(ひとみ)の美しさは、それに当てはまらない。と、彼女は感じた。
それは、強いて喩えるならば金属のようだ。
宝石が、たとえどれほど深い色合いのものであっても己の奥底まで透かし見ることを赦すのに対し、金属は決してそれを赦さない。
彼の眸は、紅い鋼のようだ。
縦に裂けた瞳孔はあまりにも細く、何人にもその奥を覗くことを赦さない。
人のものとは異なる眸は、否定できぬ恐怖と、そして悲しみを、持ち主の意志とは無関係に見る者に強いる。
耐えかねたように眼を逸らしたのは、彼自身のほう。
あらぬほうを見やる紅い眸が、気まずげに、悲しげにさまようのを彼女は見たが、それさえも、すぐに瞼の下へと消えてしまう。
ああ、やっぱり。
確信が、彼女の心を冷やす。
彼は、自分の眸は「見る者に恐怖の念を植え付けるためのもの」だと、そう思い込んでいる。
それもまた事実。
彼自身が望んで、手に入れたはずのもの。
すべてを圧し拉ぎ、ひれ伏させる「力」の、象徴ともいえるそれ。
かつて、煮えたぎるさまざまな負の感情を湛えた眼を、真っ直ぐに、彼女に……彼女たちに、彼は向けてきた。
それは「威嚇する」というほど、あからさまなものではなかったけれど……、
だが、自分の眼の持つ力を、都合のよいものであると思ってはいただろう。
ここに至って、おそらく初めて彼は己の眼光を疎ましいと思い……、
だが、それを抑えることはできず、せめて彼女から顔を背け、瞼を下ろすしかなかった。
己の眼が、彼女を傷つけてしまうことを恐れて。
「……弱虫」
囁かれた言葉に、彼は思わず眼を戻す。嵌められた、と思う間もなく両手で頬を挟まれる。
この世のあらゆる穢れを映してきた、己の眸の紅と対を成すような、一点の曇りもない、彼女の瞳の蒼。
見てはいけない。覗いてはいけない。……穢してはいけない。
だが、
「ちゃんと見て」
咎めるような、愛しむような彼女の声は、否やを赦さない。
「ちゃんと見て。わたしはあんたの眼を、怖いなんて思わないから。……だから」
戦きを滲ませた彼に、痛みに耐えるかのような笑みを彼女は向けた。
「……だから、あんたも怖がらないで」
。。。。。
三本目でございます。
「短文」というにはギリギリの長さかもしれませんね。
相も変わらず「冥香設定」の「彼」と「彼女」でした。
もう説明いらないですよね?(笑)
では。
|
|
|