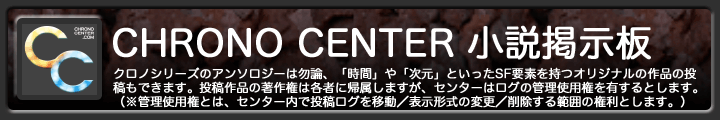| |
「まぁ!あなたが噂の猊下!きゃー!どうしましょ、あたしの好み〜♪」
僕がカイルのもとに戻ると、そこにはとっても綺麗な女の人がいた。でも、声がどう考えても…男。スタイルも服装もルックスも完璧なのに、あれは絶対男!!
その女もどき男は僕に駆け寄って力任せに抱きついてきた。
「ちょ、ちょっと離してください!僕はそんな趣味ありません!!!」
「まぁ〜、照れちゃって、素直にあたしの美貌に一目惚れって仰いなさい!」
「うわ〜〜!ちょ、ちょっと、顏近づけない!ぎゃー、か、カイル!助けてくれー!!!」
その時僕の体はふわりと浮いた。
いや、ひょいと持ち上げられたというのが正しい。
僕の体は誰かの手によって軽々と持ち上げられたかと思うと、すぐ近くにそっと降ろされた。
「ダーグ!おまえはもっと静かに出来ないのか。」
僕を軽々と持ち上げた人は、長身のメガネをかけたとってもインテリー!な感じの、いわゆる流行のメガネ君なにーちゃんって感じだった。髪は9:1分けで短く揃えられているサラサラとした濃紺で、見たことの無い毛色なのに違和感が無く自然だった。それより、彼の瞳の色もまた綺麗な青で、神秘的な輝きをたたえていた。
「いやん、クウォルツお兄様。あたしが可愛いものに目が無いのは知ってるでしょん♪」
「猊下に向かって何を言っている。」
呆れたふうにクウォルツと呼ばれたメガネにーちゃんは言うと、僕の方を振り向いた。
「申し訳ありません。我が弟達の無礼をお許しください。特にそこで寝ているカイル!!!」
クウォルツの声は、一発で長イスでグースカ眠っているカイルを起こした。
「あ、兄上!?俺眠ってません!!!」
「…猊下がもう少しでダーグの毒牙に襲われるところだったぞ。」
「え!?あ、ダーグ!!てめぇ、また趣味の悪いことを!!!」
そう言って立ち上がると素早くダーグの胸ぐらを掴みかかる。
ダーグはというと、そんなことにも動じずマイペースに、
「あら〜、良いじゃないのよぉ〜♪減るもんじゃないんだしぃ〜♪」
「減るもんだ!お前の薄汚い手をシグレに向けるな!!」
「まぁ、つれないわぁ。そう、あたしは悲劇の乙女。こんな哀しい瞬間は…可愛いモノに癒されたいと思う複雑な乙女心を理解出来ない弟を持って、あたしってホントに不幸ね。しくしく。」
一連の男達の行動に半ば引きつつも、僕は彼らが兄弟であるという事実に妙な納得を覚えていた。いや、だって、カイルと良い、ダーグと良い、すげぇマイペースじゃん。それにこんな弟達を持っていても動じないクウォルツさんも相当に…。
「あ、あのぉ、皆さんはご兄弟なんですね。」
「そうよぉ!不本意だけどこの馬鹿カイルとクウォルツお兄様とは兄弟なの〜♪」
「お、お前なんかアニキじゃねぇ!!」
「あらぁ、あたしをお姉さまと認めてくれるの!まぁ!嬉しいわぁ〜♪」
「認めない!断じて認めん!!!」
…あぁ、だめだこりゃ。
僕は二人の掛け合いに付いていけないものを感じながら、まだ新たに現れた兄弟達に挨拶をしていないことに気付いた。ここはやっぱり暫くお世話になるわけだし、しっかりと挨拶をした方が良いだろう。
「あの、もうご存じかもしれませんが、しばらくこちらにお世話になります、シグレ・クルマと申します。宜しくお願いします。」
僕の言葉に耳をピクつかせると、すぐにカイルとのじゃれあいをやめてダーグがまず反応した。
彼は突然キリリとすると、イメージとは裏腹にまともに挨拶をしてくれた。
「私は、ダーグスタ・ブレニム・ドーリア。このアスファーンの第二王太子です。普段はドーリアの領主として働いておりますが、本日は用事できております。我が領地へ立ち寄られました際は是非お呼びください。」
そう言うと片膝を付いて、よくある貴族の礼って奴?あれをしてくれた。実際に目前でやられると、なんか妙に照れ臭い。つか、恥ずかしい。
「では、私の番か。私はクウォルツェル・リード・スタインベルト。この二人の兄です。普段はこの国の執務をしています。何かあったら私に仰ってください。猊下。」
「あ、はい。お気遣い有り難うございます。」
しかし、ここはこれで分かったことだけど、真面目に王国ってやつみたいだ。専制君主制って奴?…イマイチよくわからない世界だけど、暫く住むってことは…この人達と上手く付き合っていかなきゃならないんだよな。
僕がそんなことを考えていることを知ってか知らずか、彼らの長兄であるクウォルツさんはダーグさんの腕を掴むと僕の方を振り向いて言った。
「では、猊下。私達は仕事がありますのでこれにて。」
「あ、はい。」
「さぁ、行くぞ、ダーグ!」
「いや〜ん。もぅ〜。」
クウォルツさんはダーグさんを強引に引っ張って書庫を出ていった。いや、実際の見た感じはとっても軽々としているんだけど、ダーグさんの体格を考えると…あれは絶対普通の力加減ではないはず。その証拠にダーグさんは最後まで未練たらたらで、もうホントに渋々といった感じだろうか。
カイルはそれを見届けると僕の方を振り向いた。
「シグレ、本は決めたのか?」
「あ、はい。」
「ははは、そう畏まるなよ。シグレ。」
「え、うん。」
「行くぞ。」
カイルはそう言うと、颯爽と前を進む。
その姿は本当に堂々としていて、僕とは大違いだと思う。
なんであんなに自信たっぷりなんだろう。
やっぱり王子様として生まれたからかな。
彼が通るとみんな端に寄って礼をしたり、そうじゃなかったら会釈をしている。宮廷に務めている人ってのもカイルに負けず劣らず品が良いけど、やっぱオーラの差なんだろうか。
僕がそんなことを考えていると、不意に彼が振り向かずに話しかけてきた。
「シグレは、本当に何もわからないのか。」
「え、…うん。この世界のことはわからないよ。」
「…そうか。なら、どこなら分かるんだ? 父上に話した二ホンという国のことか?」
「…そうかもね。」
彼はその後は何も聞かずに歩き続けた。
そして、僕らは城の三階の西側の部屋の前に来ていた。
「シグレ、この部屋がお前の部屋だ。」
「え、僕の部屋。」
彼は頷くと鍵を開け扉を開いた。
開かれた扉からは夕日が差し込み、白い壁は黄金に染め上げられていた。その広さは学校の教室の二つ分くらいありそうだった。
カイルは中に入ると窓を開きテラスに出た。僕もいそいそとそこに続く。
「どうだ、綺麗だろ。」
「うん。」
山の上にある城の三階という眺望は本当に息を飲むほど綺麗な景色だった。沈み行く赤方変異した大きな太陽は黄金のオーラで世界を包み込み、街は勿論、全ての野山の緑を金色に輝かせていた。
都会に暮らしていた僕からすれば、確かにここは異世界であると同時に秘境と言えた。
「なぁ、お前の知っている日本という国は、こんな景色が見られるのか?」
「…僕の住んでいる世界は、ここにも負けないくらい沢山の人がいるけど、こんなに綺麗じゃないよ。」
「はは、そうか。なら、アスファーンの勝ちだな。」
「えー、勝ち負けの問題なのー?」
僕の疑問に彼は答えず、静かに室内に戻っていった。
僕は仕方なく彼の後に付くしかなかった。
カイルはその後簡単に僕に城の人の呼び方とかを教えてくれた。…こうして接してみると、最初は「俺が絶対」って感じだったけど、案外良い奴なんだなって思った。
「さて、明日だが、シグレに会わせたい人がいる。」
「会わせたい人?」
「そうだ。俺の母上だ。」
「あ、お母さんか。うん分かった。」
「じゃあな。」
カイルはそういうとまたまた颯爽とずんずん歩いて出ていった。
扉が閉まった後、僕は思わず一息溜め息を吐いた。
眠りから覚めたら変な田舎にいて、そこに現れたのは中世貴族のハリウッド張りなにーちゃん。そして、初馬乗り、王様、おかま、紺色髪のおにーさん。…有り得ないよなぁ。普通。
僕は望んでいたはずの非日常を味わいながら、それを受け入れるなんて気持ちになれず、ただ脱力感にも似た疲労感に襲われてとぼとぼとベッドに足を運んだ。さっき、ホントは食事も誘われていたんだけど、正直食事もする気になれなかった。兎に角疲れたってのが本音だ。
だが、休もうとベッドを見て僕は棒立ちになった。
「………あるんだな。まじで。」
そこに有ったのはお約束とでも言うべきか、天蓋付きの大きなキングサイズの純白のベッドが置かれていた。なんか見ているだけで圧倒されるというか、自分が寝ている姿を想像するとおぞましいものを感じつつ、でも眠ってみたいとも思う好奇心をどう言い表したら良いのだろうか。
それでも疲れというものは凄いもので、それはもう吸い寄せられるように僕の本能はベッドを欲し、ベッドもまた触れた僕を掴んで離さないような心地よい肌触りを伝えてくる。
僕は程なくしてベッドの誘惑に落ちた。
|
|
|