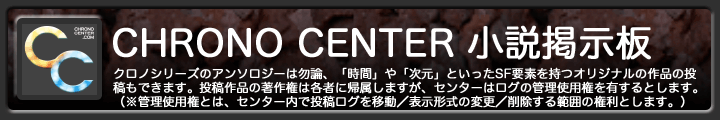| |
「…どこだ、ここ。」
僕はどういうわけか空の上にいた。
何がどうなって浮いているのか分からないが、じたばたしてみた所で落ちないことは分かった。
なんとなく薄曇りの夕暮れ時だろうか、沢山の車が飛んでいる。SF映画みたいにさも当然の様に浮いているんだ。
世界全体が鉛の様に鈍い輝きを帯びて太陽の光を照り返す。その姿は異様だが偉容でもある。こういうのを未来って言うんだろうな。
ふと近づいてみたいと思ったけど、眼下の都市へはやっぱり降りることは出来ない。下を向こうが何をしようが、ただただくるくると回っているだけ。懸命な努力も虚しく疲れだけが残った。
僕は仕方なく見ているしかなかった。すると突然視点が上昇し始めた。その早さは凄まじい重力を伴うような速さで、僕が打ち上げられている様な圧力を感じ目を閉じた。その圧力は10秒くらいだろうか。突然それが収まったので目を開けると、そこは宇宙だった。
宇宙から見た地球なんて初めて見る。
確かに有名な宇宙飛行士が残した言葉のように青い宝石。ここが僕の生れた世界。
人生にとても印象深い感動のシーンを上げるなら、ここは間違いなくその場所の一つになるに違いない。そんなことを思っていると、突然前方に何かの光が一つ走った。
いや、それだけじゃない。
一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、十、十一、十二…もう、無いかな。
その光はゆっくりと世界中に散らばって降りていく。その時地上からも幾筋もの光がまるで出迎えるかのように走る。だけど、それは途中で衝突して閃光をたて始めた。そして、地上の光はまもなく消滅し、宇宙からの光は地上に到達すると緋色の閃光をあげて、まるで核爆発を起こしたような巨大なドーム型の爆発を作り出すと、その波は波紋が広がるように広域に広がった。
その爆発は他の地域に落ちた光からも生じ、次々に世界を飲み込んでいく。
僕は何が起こっているのか理解できなかった。
言えることは、綺麗な迫力ある映画のワンシーンにしか見えないってこと。でも、僕がこの真空の宇宙で呼吸して漂っているという非現実的な現象を除けば、視覚に映っているそれはとてもリアルな空間での出来事だった。
僕はアスファーンの書庫で見つけた本の記述を思い出した。
「…古の12の神。」
これがソレなのか?
だとしたら………あんまりだ。
僕の目から思わず涙が溢れてきた。
そこに、何処からともなく声が聞こえる。
「…下。猊下。」
僕は目をゆっくりと開いた。
目前にはとても綺麗な金髪のお姉さんの姿。白いぴちぴちの綺麗なレースの刺繍のが入ったワンピースを着た彼女は、僕を膝枕していた。…って、膝枕!?思わず僕は飛び起きた。
「あ、あの、ぼ、僕は一体!?」
飛び起きた僕の周囲には執事のおじいさんに、カイルの姿もある。
カイルは複雑そうな顔をして苦笑交じりに僕に言った。
「…さすがに気絶は無いぞ。まぁ、姉上も年頃の女性が聖職者と混浴するという状況は話しにならないが。」
「なぁに、カイル。聖職者ですもの、間違いはないじゃないですの。ウフフ、ね?猊下?」
「え…」
僕はどう応えていいか分からなかった。
というか、あれ、僕、裸!?
「う、うわ!?あ、あの、ふ、服は!?!」
「ほれ。」
僕はカイルから服を慌てて受け取った。
なんてこった。失敗するにも程があるよ……。
「あ、ありがとう!っていうか!みんな出ていってください!!!」
「えー!今更良いじゃないですか〜!私は猊下の全てをもう知った仲ですのよぉ〜?」
「す全て!?って違う!そんなの絶対ダメ!っていや、あ、もう!!!はやく出ていってください!!!」
僕は力の限り叫んだ。
彼らは僕の剣幕にさすがに応じてくれて、渋々という感じだけど外に出ていってくれた。
その後の僕は、泣きたい様な気持ちを胸に仕舞いながら、服を広げてみた。
「…え。」
僕は思わず凍った。
いや、これで終わるとは思わなかったけど、これは…。
一挙に到来する情けなさとやるせなさと虚しさと…僕はさすがに自分を呪った。
|
|
|