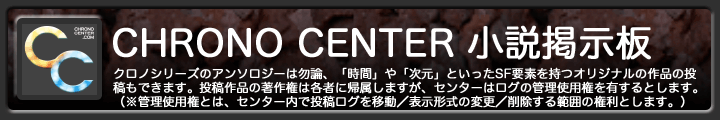| |
「ジュリエットさんが…て、本当にどういうことなんですか?」
「…それ以上は秘密ですわ。ただ、この子を産んで後悔はしていません。こんなに男らしく育ったんですもの。」
僕は詳しく聞くのはやめた。
彼らには彼らにしかわからない事情があって、わざわざ秘密にしているんだろう。そこに僕みたいな外野が不必要に情報に触れることは良くないって思った。何より、誰が聞いているともしれないここでかれらが秘密にしなくてはならない事情を聴くことは、少なくとも適切な場所とは呼べない。
僕は適当に話題を変えることにした。
「わかりました。えっと、では他に幾つか聞きたいことがあるんですが、いいですか?」
「はい、猊下。」
「その、この世界って戦争とか無いんですか?」
「戦争?……ございますわ。」
ジュリエットさんはそういうと哀しげに近くの花壇に咲く花の方を見た。
その花は黄色いすいせんの様な可愛らしい球根草だと思われた。
「わがアスファーンはこの地域に根ざす大国として知られています。しかし、我が国と他国の外交関係が決して良好であったわけではありません。古くは漆黒の瞳の賢者様が我が国は勿論、世界を導かれたこともある我が国ですが、今はそれ以来脈々と受け継がれる通力の力を怖れ、敵視する勢力があるのです。」
「通力?」
「えぇ。通力とは自然の力と通じて奇跡を起こす能力です。元は12の力が我が国に集いましたが、今では半分の力のみで、我が国に他国をどうこうするほどの意図も無ければ力も無いのが実情です。しかし、人は持てる者と持たざる者の差を気にするものです。我が国に今でも6つの力があるということは、彼らにしてみれば脅威なのでしょう。」
なんだなんだ!?
今度は突然RPGの定番の魔法っぽいものがあるっぽい発言がでてきたぞ。
僕は内心わくわくしていた。
「あの、その通力って、僕も扱えるモノなの?」
「猊下ですか?…そうですねぇ、伝説の漆黒の瞳の賢者様は全ての力を調和したと言います。もしかしたら、猊下にも力があるのかもしれませんわ。」
「え、そうなんだ!」
僕は心の中で万歳と両手を上げた。
やっとなんとなく世界の雰囲気に合った夢の様な能力が使えそうな兆し。
「えっと、その力はどうやって使えば…」
その時、城門から駆けてくる1人の兵士の姿があった。
その兵士は城内を目指していたようだが、僕らを前庭に認めて駆け寄ってきた。
「バルムドゥール殿下!カールグリーフが我が国に兵を向けてきました。」
「何!?で、今何処だ。」
「は、現在、ドーリア領付近まで接近。ドーリア公が軍を率いて対峙しておられます。現在スタインベルト軍が援軍に向かっているという報が入っておりますが、カールグリーフの背後にエメレゲが動いているのではないかと…。」
「ガイファーか。よし、分かった。陛下の所へは俺もお前と一緒に付いていこう。来い!」
「は!」
そういうと、カイルは兵士を連れて駆けて行った。
僕は呆然とその状況を見ているしかなかった。でも、隣のジュリエットさんは哀しげな表情のまま花を見ていた。
戦争が起こる。
それはシミュレーションRPGみたいな争いなのかも知れないけれど、失われるのは本物の命。…僕は背筋が凍る様な嫌な感じや急激に冷や汗みたいなものが吹き出すのを感じた。
遊びじゃない。
誰かの命を失うなんて有っていいわけが無い。どんな人にも家族がいて、友達がいて、哀しむ人がいる。兵士だけじゃない。戦争をすれば沢山の人が家族を失い、命を消していくんだ…。
…止めなきゃ。
僕は無性に何かに突き動かされるように動いていた。
「…猊下?」
気がついた時には馬小屋に走っていた。
|
|
|