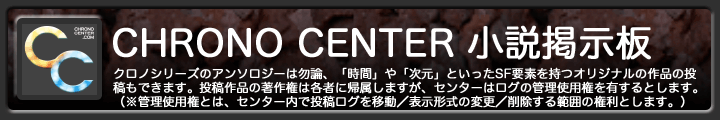| |
僕たちは城の前庭に来ていた。
ここは色とりどりの花が咲き乱れるとても手入れの行き届いた庭園で、花の香りが風で運ばれてとても心地よい空間だった。そこに用意された白いテーブルに日傘と白い椅子が3脚。四角い白いテーブルには、東側を背にジュリエットさんが座り、南側にカイルが、北側に僕が座った。西側には給仕の係りの人がお茶とお菓子を出し入れするのにやってきてくれていた。
僕は出されたお茶を飲んだ。
「美味しい!これ、なんていうお茶なんですか?」
「これはミレディティーですわ。」
「ミレディ?」
「あぁ、あそこに生えている赤い花がミレディ。」
僕はジュリエットさんの指し示した方向をみた。そこには確かに赤い花が咲いていた。なんとなく薔薇に似ている。つまり、これはローズティーってことかな。
「…さて、そろそろ本題と行きましょうか。カイル。」
彼女はそう言うと、カイルの方を向いた。カイルは彼女の言葉に頷くと僕の方を向いた。
「シグレ、お前の国は二ホンと言ったな。」
「うん。」
僕が頷くと、ジュリエットさんはおもむろに本をテーブルの上に置いた。その本はとても古くてくたびれていた。
「これは?」
「我が国に代々伝わる古文書です。ここには創世の以前の世界のことが書かれています。」
「これをどうして僕に?」
「とにかく開いてみてください。」
「うん。」
僕はその本を手にとり、ゆっくりとページを開いた。そこには僕にもわかる日本語で文字がかかれている。内容は日記のようだ。
今日、連邦政府はガーディアンフォース12の使用許可を出した。…もう、これしかないのか。私はなぜあんなものを見つけてしまったのだろう。いや、まだ終わったわけではない。
宇宙の動向が緊迫してきた。連邦木星基地がやられた。奴らは化け物か。ガーディアンフォース12の発射が間に合うかギリギリか。プランBも実行せざるを得ないか。
アステロイドベルトを越えたという報告があった。奴らの技術をトレースしているが、それを上回るスピードで迫っている。連邦艦隊は火星に防衛ラインを張ったが、時間稼ぎにもなるかどうか…。
今日、プランBを実行に移した。我が子にはすまないことをしたが、人類は今消えるわけにはいかない。彼らにも良心があるならば、我々の世界を…いや、もはやここまできてしまったのだ。楽観は控えるべきだ。…もうすぐ日本に帰る許可も下りる。
火星軍が全滅したらしい。もう数日もせずに来るだろう。出来る限りのことはした。我が人生に悔いは無い…いや、一つあるか。最後くらいはリンと一緒にいたかった。愛している、リン。
来たか。月防衛ラインを突破される前にはなんとか間に合った。ガーディアンフォース12を使っても世界の破滅は免れない。だが、彼らもただでは済まない。ざまあみろ。最後は我々が勝つ。
この後の記述は無かった。
この日記の文字は印刷された文字のようで、この作者の死後に作られたのだろうか。
推測するに、これは「古の12の神」と関係があるんだろう。
「猊下、この本の内容は分かりましたか?」
「あ、はい。」
「では、どんな内容かお話してくださいませんか?」
「え、あぁ、わかりました。」
僕は本の内容を聞かせた。二人は静かに僕の話を真面目に聴いてくれた。
「…姉上。」
カイルがジュリエットさんの方を向いた。ジュリエットさんは頷くともう一冊の本を出した。
「猊下、この私が持っている本はあなたの読まれた本の翻訳本です。今あなたが読まれた本を読める方は、もはやこの世界には残っていないのです。」
「え、じゃぁ、その翻訳は?」
「これは何百年も昔の時代に訳された本の写本です。ですからこの本に書かれている内容と少しズレがありますが、大筋で猊下の読まれた原板と違いありません。…猊下、申し訳ありません。」
突然ジュリエットさんが僕に深々と謝罪した。僕は突然過ぎて何がどうしたのかさっぱり分からなくて慌てて頭を上げるように促した。
「あの、何故謝るんですか?」
僕の問い掛けにカイルが口を開いた。
「これは俺が言い出したことだ。お前が二ホンという国の名を出したから、大昔の国の名前じゃないかとおもってな。姉上の統べる教会に本は保管されている。だから姉上に無理を言って持ってきてもらったのさ。」
「それじゃ、僕を調べる為に?」
「あぁ。」
「ごめんなさい。猊下。」
僕は呆気にとられた。
あんなにコミカルなまでにとぼけた人達だと思ったのに、やっぱり彼らは政治家って人達で、僕が考えている以上に色々なことを考えている人達だったんだ。いや、確かにどこの馬の骨とも知れない少年にこれほどの待遇をする国ってのも変だけどさ…。
「謝ることはないよ。で、僕のことはどう思ったんですか?」
僕の問い掛けにジュリエットさんは、
「猊下は、やっぱり猊下でした!」
「え!?」
「もう、この古代文字を解読できちゃうだけで最高ですわ!」
「あららら…」
何か知らないけれど、僕はもっと信じてもらえることになったらしい。
これは喜んでいいのやら…。
僕はぽりぽり頭を掻きながらどうしたものかと考えていると、ふと昨日の言葉を想い出してカイルに尋ねた。
「あの、カイル。君のお母さんの所へ行くんじゃなかったっけ?」
「そうだ。」
「じゃぁ、会いに行こうよ。」
「だから、来ただろう。」
「え?」
僕は頭が混乱した。
ここにいるのは僕とカイルとジュリエットさん。他には給仕の人達くらい。
「えーと、どこ?」
カイルは僕の問い掛けに指を指し示した。
その先は…マジ。
「えーーー!!!!っていうか、だって、兄弟なんでしょ!?」
「そういうことになっている。」
「ウフフ、ひみつよ〜♪」
「な!?えーーー!?!っていうか、さっきカイルは年頃って!?」
「適齢期には変わりないだろう。」
「………いや、そうだけど…って違うでしょ!?」
あぁ、なんか頭痛くなってきた。
僕はこの王国の家族構成に激しく疑問を感じつつ、なんとなくこれだけでは済まされない暗雲を感じながら、苦笑を禁じ得なかった。
|
|
|