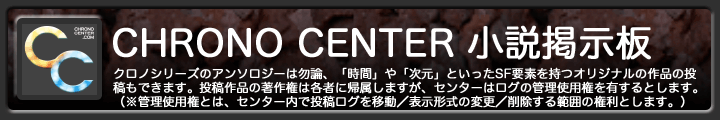| |
出された服は白タイツに白いぴっちりシャツ。
そして、頭からすっぽり被って前後にばさばさいっている、ドラ○エの僧侶が来ているようなアレ。
そりゃ賢者ったら聖職者なのかもしれないけれど、僕別に悟り開いたわけでも無ければ、賢者って自覚すら無いんだけど…。しかし、置かれた服はこれのみ。まさか白タイツ白シャツ姿だけで出るわけにもいかず、とりあえず下着だけまず穿いた。
ただ、下着が白ブリーフというのがまた…なんで今更僕は…。だけど、コイツを穿いてみて思ったのだけど、このまま誰かを呼ぶくらいなら白タイツコスプレの方がまだマシだと思えてくるのだから、なんとも術中にハマっているような気がしてならない。
いや、絶対罠に決まってる。…って力説する自分が虚しいけど。
仕方なくコスプレした僕は脱衣室を出ることにした。外にはあの3人が待っているに違いない。もはや裸まで晒したと半ば開き直りも入りつつ、思い切って僕はドアを開けた。
そこには案の定3人の姿が…、
「まぁ、猊下!よくお似合いですわ!」
「孫にも衣装って奴だな。」
「サイズもぴったりでございますな、猊下。」
三人三様に褒め言葉が飛び込んできた。でも、表情は絶対笑いを堪えている。…というか、あのお姉さんの顔を見たら、再度自分の痴態を晒してしまったことを急激に思い出す。さすがに簡単に割切れるものでは無いらしい…。
「あ、あの…。この服以外ありませんか。」
「えぇ〜!お似合いですよ〜!勿体ないわ〜!」
「そうだぞ!こんなおもし、もとい素晴らしい絵は見たことないぞ俺は。」
「お気に召しませんでしたか、猊下。」
し、白々しい。くそぉ、完璧に遊ばれている。
僕は沸々と湧き上がる怒りを感じていた。もはやここまで壊れてしまえば何も怖くない。
「すぐに僕の服を乾かして返してください。それがダメなら、他のあなた方が着ている様な一般的な服を用意してください。僕は悟りを開いたわけでも無ければ、賢者であると言った覚えはありません。」
僕は今出し得る最大級の憎悪を燃やした表情で3人を睨み付け言い放った。それは3人を一瞬で串刺しにする。
「あ、あぁ、分かりましたわ猊下!ほ、ほら、カイル!あんた服あるでしょ!」
「あ、姉上!?お、ぉお!わ、わかりました。い、今すぐ用意しよう!!」
「バルムドゥール殿下、殿下の服では大き過ぎます。私めが殿下のお小さくなった服を取寄せさせますので、お任せください。」
「おう、ボブ、至急頼むぞ!!」
その後15分程してカイルにボブと呼ばれていた執事のお爺さんが、一着の服を持ってやってきた。その服は青を基調にした制服みたいな服だった。袖などには銀糸でラインが入っていて、さすが王子様って感じの豪華さもある。…これはこれでちょっと恥ずかしかったけど、白タイツ姿よりは天地の差ほど違いがある。
僕はその服に再び脱衣室で着替え直すと、3人のもとに戻った。
「まぁ、猊下!カイルのちょっと昔を見ているみたいで可愛い!」
「ほぅ。」
「いかがでございましょう、猊下。」
「うん、今度のはとても着心地が良いです。わがまま聞いてくれて有り難うございます。」
「いえ、お礼でございましたらバルムドゥール殿下へお伝えください。では、私はこれにて失礼させて頂きます。」
そう言うとボブさんは礼をして静かにその場を去っていった。
「えっと、あの、あなたはカイル殿下のお姉様なんですよね?その、先程は本当に申し訳ありません。」
「いいえ。私も聖職者としてこの国の司祭をさせていただいております身。間違いなど起こり得ません。ご安心下さいませ。」
「え”!?司祭!?!」
「はい、猊下。宜しくご指導賜りたく申し上げます。」
そう言うとお姉さんは深々と礼をしてきた。慌てて礼を返す僕。
礼を直ると、お姉さんは続けた。
「それと、申し遅れました。私はジュリエット・マルーン・アスファーン。この子達の一番上の姉でございます。ジュリーとお呼びくださいませ。猊下。」
ニッコリと微笑んだジュリーさんは、今までの15年の人生の中で奇跡的な程の綺麗な笑顔で、こんな人にこれから他に会う機会があるのだろうかと思うほどの絶世の美女だった。
「んと、えー、ジュリーさん…って、その、一番上?」
「はい。私が我が王国6人兄弟の一番上でございます。」
「六人兄弟!?」
「あら、存じ上げませんでしたか?猊下。」
「あ、はい。初耳です。」
僕は驚いた。クウォルツさんが一番上で、その下くらいだろうと思っていたということもあるけど、その前にこの兄弟が6人もいるということが…。カーライル、クウォルツ、ダーグスタ、ジュリエットの4人は見たけど、この他に二人…どんな人なんだろう。というか、彼らの年齢構成が分からないのでイマイチポジションがハッキリしないけど。
「左様でしたか。では、ここではなんですから、お食事でもご一緒にしながら、お話でもいかがです?」
「あ、別に僕はそれほどお腹も空いていないので…」
「では、ティーと菓子ではいかがでしょうか。」
その時のジュリエットさんの表情は、世の男という男全ては絶対服従したくなるんじゃないかと思えるほど、なんだか断るのが勿体なく感じた。カイルも微笑を讚えて彼女に従っているようだし、ここは彼と同様に従っておくとしよう。
え?僕が単に食事がしたいんだろって?違うよ、仕方なくだよ、仕方なく。…とは言いつつも、確かに僕の心は踊っていた。
「あぁ、はい。では、お言葉に甘えて。」
|
|
|