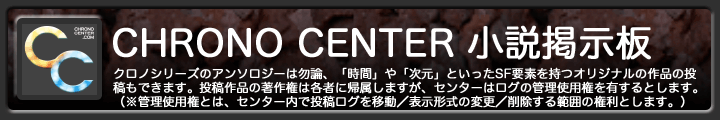| |
カイルは近くの街道に馬を待たせていた。
僕は彼の後を仕方なく付いてゆくことにしたけど…
「さぁ、乗れ」
「え?」
「なんだ、馬にも乗ったことがないのか。よし、まず乗せてやる。」
彼はそう言うと僕を先に馬に跨がせた。丁寧にまず左足から鐙(あぶみ)に足を掛けて、勢いをつけて弾むように鞍の上に跨がるように教えてくれた。彼は初めてにしては上手いと褒めてくれた。…ちょっと自慢できる?
その後はカイルも後ろにまたがり、僕の後ろから手綱を引くと、馬をゆっくり歩かせ始めた。
馬の上から見る景色は面白い。
僕の背の高さより高いってのもあるけど、長い首がフラフラと揺れ動いて、まるで喜多方ラーメン屋とかに置いてある福島の民芸品の赤べこの首が動いている様な感じ。そう思うと、あぁ、昔の人って凄いんだなぁとか今更意味不明な感心をしてみたり。
何より気持ちいい。
心地よい爽やかな涼風が吹きつけ髪をなでる。
「しっかり掴まってろよ!」
「え”!?」
カイルは唐突にそう言うと、手綱をしっかりもって足で馬の腹を叩いた。
「うあ、おぉぉおぉぉおぉおおおおおおお!?!な、な、は速いってぇ!!!」
「はっはっはっはっはっは!」
僕が動揺しているのを楽しむかのように、奴は笑いながら街道を道なりに走らせていった。
-----------------
「うぅ、マジかよぉ。」
「おい、見えてきたぞ。」
「え、あ!街だ…っつか、街!?!」
「あれが、アスファーンだ。」
「…アスファーン。」
前方に見えてきた街は四方を城壁で囲んだ城塞で、周囲は緑豊かな山で囲まれていた。
城は奥に有り、その下が城下町って感じだろうか?…でっかい門があって、その前には堀まである典型的なお城って奴?
「あ、あの、カイル、ここが君の家?」
「はっはっは、あの奥に見えるだろう?あの城が俺の住む城だ。アスファーンは緑豊かな国だ。こんなに豊かな国は他に無いぞ。きっとお前も気に入る。」
彼はそう言うと微笑みを浮かべて馬の足を再び速めた。でも、どうやら彼には気付かれているらしい。僕のお尻がちょっちやばい状況なのを察してくれたのは…よしとしよう。
近づいてみるとめちゃくちゃデカイ街だった。
門は平時は開かれている様で、行商人とかが自由に行き来できるっぽい。一応検問はあるみたいだけど、カイルは王子様だからか顏パスOKだった。
街の中に入ると沢山の商店が並び、多くの家がひしめいていた。そして、何かを焼く匂いや油臭い匂いとか色々な生活臭って言うんだろうか?…独特の匂いを感じて日本とは違うんだと改めて思った。
特に…ここは産業革命前って感じだろうか。電線も無ければ自動車も無い。交通手段は馬や馬車や荷車。人々は歩き、自転車さえも無い始末。どうやら本当に中世って感じ。
でも、カイルが言う通り、街は豊かそうで人々の活気で溢れていた。確かに悪い感じはしない。でも、そんなことを考えているうちにどんどん街も通り過ぎ、城の門前に着いた。
「カーライルだ!開門!」
彼がそう言うと、ごとごとと門が開かれた。
彼は完全に開かれたのを確認すると、馬をゆっくり進めて門をくぐった。そして、潜り終えると手綱を引いて馬を止めた。
「降りるぞ。」
「あ、はい。」
そう言うと颯爽と格好良く彼は馬の背から下り立った。
僕はおっかなびっくりそぉっと静かに降りるので精一杯なのに。
そこに兵士らしき人が近寄ってきてカイルに尋ねた。
「殿下、こちらの方は?」
「俺の友人だ。」
「おぉ、ご友人の方ですか。」
「あぁ。馬を頼む。」
「は!」
兵士はカイルの命令に敬礼して従うと、すぐに馬を引いて厩舎の方へ連れていった。
カイルが僕の方を振り向く。
「…ふむ、付いてこい。」
「あ、はい。」
僕は彼の後を付いて歩いた。
さすがに長身なだけに歩幅が長い。あっという間にさっさと歩いていってしまうので、半ば小走りに僕は彼を見失わないようにぴったりと張り付くというと変だけど、置いて行かれないよう歩いた。
城内へは裏口から入った。裏口は城の側面の台所にあり、たぶん食材とかを倉庫から取寄せたりするために使っていると思われた。
中ではフランスのシェフみたいなコック帽をかぶったおっさんと、それに従う若い衆って感じの人達がいて、カイルが入っても気にせずに気楽に挨拶をかけて仕事に専念している感じだった。まぁ、この城の働く人全ての胃袋を考えると…確かに構ってられないよな。
カイルが歩くとどんな人も道を開ける。
さっすが王子様。やっぱ「俺が決めるオーラ」は伊達じゃない。
でも、その後に僕に対する不可解そうな視線がちょっと痛いかも。…まぁ、仕方ないけどさ。
カイルは何処にも立ち寄ることなく一つの部屋の前で止まった。そこには爺やっぽい人が前に立っていて「お待ちください」と威厳たっぷりに言っていたんだけど、そんなことお構いなしに彼は扉を開いた。
その扉の向うには大きな広間が広がり、その奥にRPGとかでもお馴染の玉座に座る人の姿があった。そう、ここは王の謁見の間。ただ、何やら準備中だったらしく化粧直し中の様だった。
それでもお構いなくという風に、カイルはつかつかと僕をつれて彼の父の前に立った。
「おい、カイル!入る時は事前に爺を通せと言っておろうに。人がこんな無様な格好の時に。」
「父上、お話があります。」
「なんだ?」
「この少年を住まわせたいのです。」
「住まわせたい少年?」
国王は僕の方を見ると、とても驚いたような顔をした。
「黒い瞳…伝説に聴く導く者の目。君は何者だい?」
「え、僕はシグレ・クルマ。日本という国から来た高校1年生のごく普通の少年というか…」
「二ホン?コウコウイチネンセイ?…わからぬ。だが、その漆黒の瞳はとても高名なる賢者の証。おぉ、我が国を神はお導きくださるというのか。」
「父上?」
「伝説に伝え聞く漆黒の賢者の話は知っておろう?」
「はい。書物によれば、漆黒の瞳持つ者、邪悪なるものを沈め、世に光溢れる道を示さん。漆黒の瞳持つ者、英知を運び、風を踊らせ、天高く舞い上がり、世を幸福に導く。」
二人の話はさっぱり理解不能だったが、彼らにとって僕は特別な何からしい。
僕の目を見てからの国王の反応はとても丁寧で、なんか僕が王様にでもなったような程の丁重な扱いになった。
「では、シグレ殿。我が城を我が家と思いごゆるりとお寛ぎください。このアスファーン王、ガメイレフ・ストラ・アスファーンがあなたの身の安全と衣食住を保障致します。」
「あ、は、はい。宜しくお願いします。」
何だかよく分からないけど、僕は唐突に賢者になってしまった。
|
|
|